・このページは、凝縮してR&Dマネジメントの基本的な考え方を説明するものです。
・利用シーンに合わせて、動画(再生速度調整や字幕が利用できます)でも、テキストでも説明を理解することが可能です。どうぞ情報収集にお役立てください。
動画による説明(約7分)
音声速度は速められます。字幕も出ます。右下の操作ボタンでお試しください。
研究開発ガイドラインのご利用、ありがとうございます。
①資料のPDFが必要な方はこちらからご請求ください。
②当社は以下のコンサルティングメニューを持っています。興味をお持ちの方は、当社のセミナーをご受講いただくか、こちらから打ち合わせ依頼をご利用ください。
・R&Dマネジメントの社内セミナー(啓蒙目的)
・研究開発クリニック(診断)
・R&Dパイプライン構築のコンサル・研修
・潜在ニーズを解決する技術マーケのコンサル・研修
・定例アドバイザリ(R&Dマネジメントに関する助言・顧問的な立場から)
・ゾンビテーマの可視化、資源再配分
テキストによる説明
はじめに
株式会社如水の中村と申します。この動画ではR&Dトランスフォーメーションのカタログに基づいて事例とノウハウについて説明をしています。ご覧いただきたいのは、R&Dトランスフォーメーションのカタログです。
今日は3ページ目からのトランスフォーメーションの事例についてご説明をしていきます。
A社の例
まず、4ページ目です。B2BメーカーであるA社の例です。
B2BメーカーのA社さん、技術者数が約800人のメーカーさんでいらっしゃいます。大企業と言える規模だと思います。大企業は上場してますので、「20XX年に利益倍増」という経営目標を投資家向けに説明していました。
公開企業はどうしても投資家向けの成長の約束が必要ですからね。これ、投資家向けの約束で公的なものです。
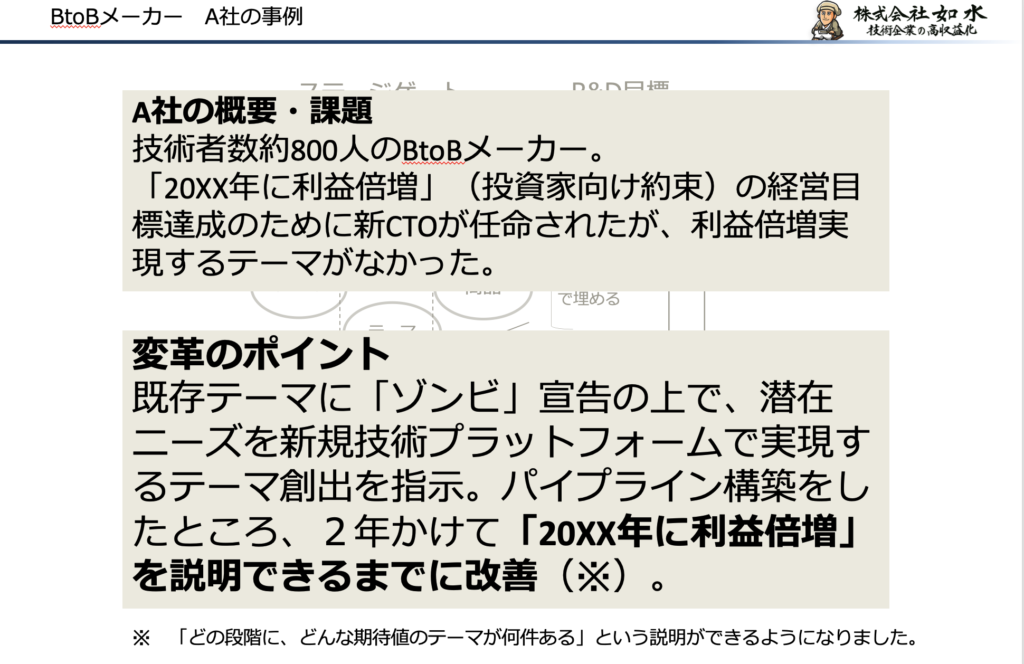
これを経営目標として対外的にも対内的にも説明してるんですけど、その達成のための新CTOを任命されたというような現状があったんですが、その達成のためのテーマというのはなくて、CTOの方がやれと社長から指示を受けているというような状況から始まったという着手前の状況がありました。
変革のポイントとしては、どんなことがあったでしょうか?
どんなことがあったかというと、800人もいますので、800人いればですね、だいたいですけども数十のテーマというのがあるわけです。
数十のテーマ、数十の既存テーマに「ゾンビ」と宣告するというところから始まりました。
「ゾンビ」というのはこの動画の後の方で説明しますけれども、要するにやっても儲からないというテーマです。
このゾンビという宣告をした上で、潜在ニーズを新規技術プラットフォームで実現するテーマソースと指示しました。
「新規技術プラットフォームで実現する」とは、意味合いとしては儲かるテーマにしなさいという指示ですね。
要するに、儲かるテーマにしなさいを指示しまして、パイプライン構築をしたところ2年かけてですね、20何十年間に利益倍増というふうに投資家向けにもそれから体内的にも説明ができるような状態まで改善するというような結果を見ました。
800人と大きな組織ではありましたけれども、その全ての人が全ての技術者が関わってゾンビを出すというテーマをすることによって「20XX年に利益倍増」ということが対外的にも対内的にも説明できるようになったというのは大きなメリットだったというふうに思われます。
B社の例
次がB2CメーカーのB社の例です。
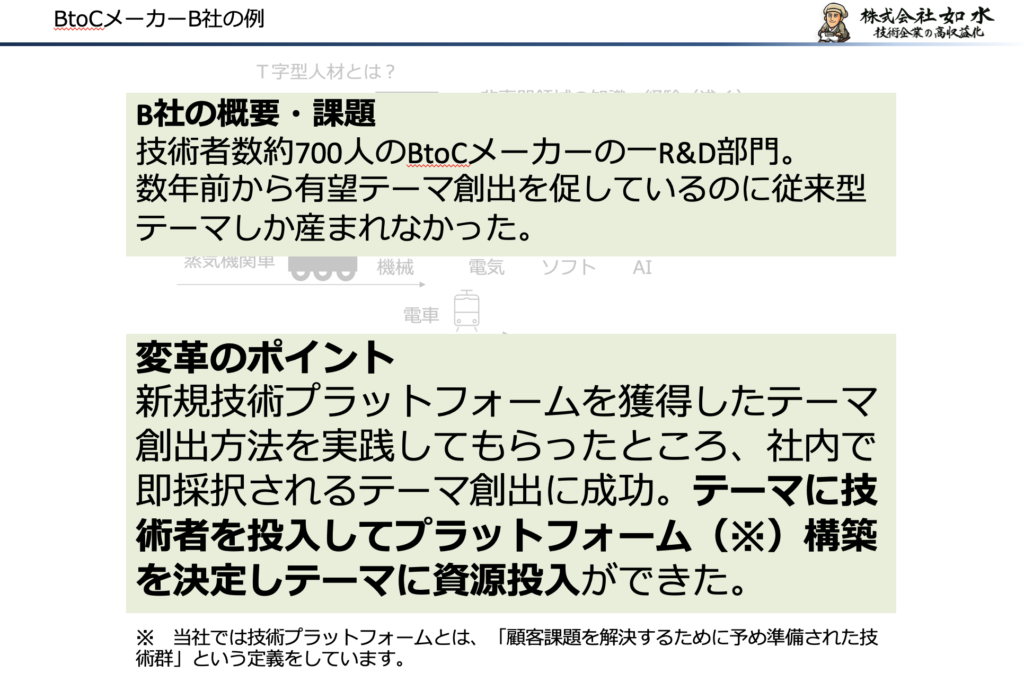
BtoCメーカーのB社なんですけれども、技術者数が約700人いるBtoCメーカーのR&D部門でした。
数年前から融合テーマ創出を促しているのに従来テーマしか生まれなかったということでA社と非常によく似ていて、700人もいれば数十のテーマがあるというのがB社でも現状でした。
けれども、そのほとんどが儲からないテーマだったということで従来型テーマだったというような話です。
変革のポイントとしては新規の技術プラットフォームを獲得したテーマ創出法を実践してみたところ、社内で即採択されるテーマ創出に成功いたしました。
テーマに技術者を投入してプラットフォームを構築しテーマに資源投入ができましたということで新しいテーマの創出、それから儲かりそうだという道筋、それからそれに対して予算資源を投入していくというような意思決定ができたということで研究開発としては非常に素晴らしい結果を生むことができました。
C社の例
次がB2BメーカーのC社です。C社はかなり大きくてですね、技術者数が約1000人のB2Bメーカーですね。
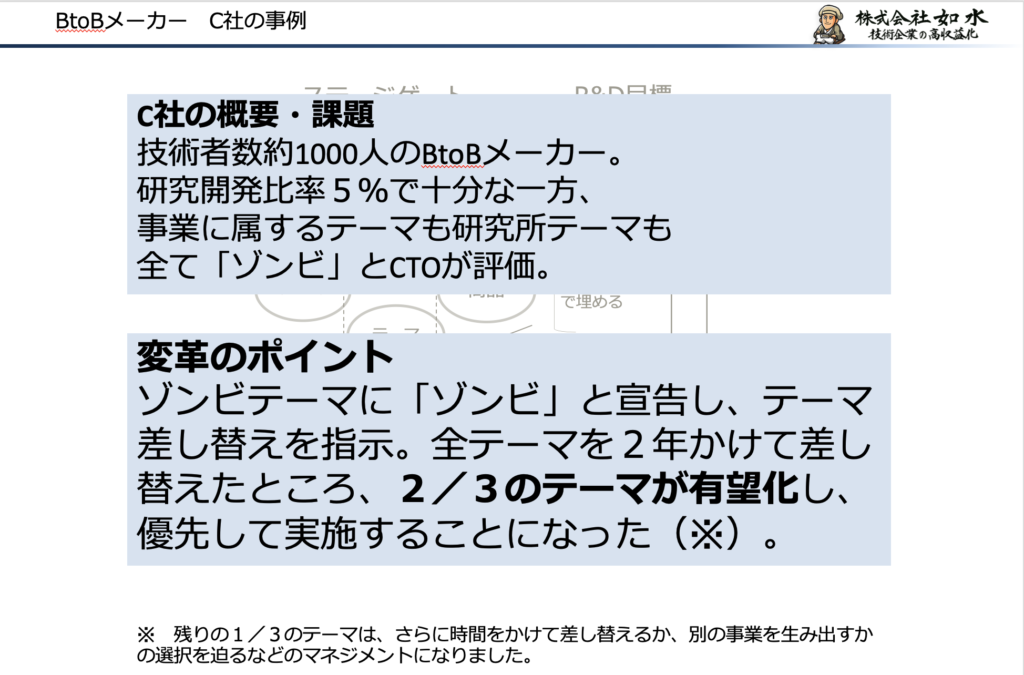
研究開発比率が5%で十分だったんですけれども、事業に属するテーマも研究所テーマも全て「ゾンビ」というふうにCTOが評価していたという例です。「これはまずい」というふうにCTOが評価した結果ですね。
そこで施策を打つことになりました。変革のポイントはゾンビテーマに「ゾンビ」宣告をするということから始まりました。
そしてテーマ差し替えを支持しました。全テーマを2年かけて一巡するような計画を策定してテーマ創出を始めるということで全てのテーマを新しいテーマに切り替えていくというふうに変えていく中で、ゾンビとしていたものも儲かるテーマに変わるということが非常に大きかったですね。
このC社は非常に大きい企業で、ゾンビというのは他にもいくつかあったわけで、それを一掃して新しいテーマに置き換えるという大変な仕事でしたが、それをやり切って「20XX年に利益倍増」という目標を実現するという結果を得ることができました。
そのためにはCTOがリーダーシップを発揮して全社的に一丸となって動いていったことが大きな要因だったと思われます。
D社の例
次がD社です。D社は最も小さくて技術者数が約100人のB2Cメーカーでした。
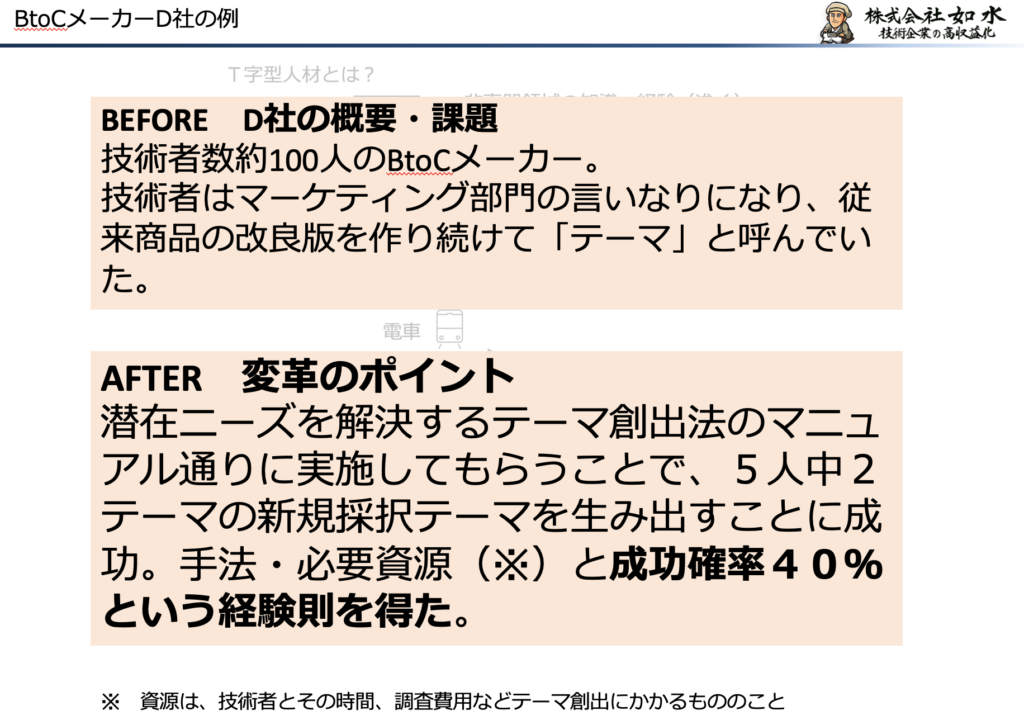
技術者はマーケティング部門の言いなりになり、従来商品の改良版を作り続けるつまり営業とかマーケティングが有用なことをやっていた営業が要求するようなこと、マーケティングが要求するようなことをそのままやっていたというようなテーマ創出の方法でした。
変革のポイントが何だったかというと、マーケティング部門の言いなりにならずに技術者自らがテーマ創出をするというようなお話でした。つまり、潜在ニーズを解決するテーマ創出法のマニュアル通り実践してもらうという意味合いです。
そうすると5人中2テーマの新規採択、テーマを生み出すことに成功しました。手法や必要資源と成功確率40%という軽減率を得たということで、この成功確率40%というのはかなり高い数字だと思われますけれども、40%くらいは作り替えることができるというようなことで繰り返せば作り替えることにかなり成功できるというようなことが体感として得られた、軽減率として得られたというような事例です。
比較的小さな会社ではありますけれども、会社全体のポートフォリオが入れ替わりそうだ、入れ替わりそうだということを予期させる非常にきっかけとなった会社の例です。
テーマ創出手法にはマニュアルがあります。
このマニュアル通り実践してもらうというのは極めて重要なことでして、皆さんの会社にも多くのテーマがあると思いますが、そのテーマを技術者が担当する技術者がマニュアルに沿って深堀りしたり調査したりそれから新しいテーマを作ったりするということで非常に強いものに生まれ変わらせることが確率的にできるということを示させるものです。
まとめ
100発100中とか絶対に直りますとかそういった手法では残念ながらありませんけれども、確実にこのR&Dトランスフォーメーションを行うことで技術ポートフォリオあるいはテーマポートフォリオを変えることができて、将来的には、「20XX年に利益倍増」という経営目標とか投資家向けの約束というのを達成することができます。
このようなR&Dトランスフォーメーションのメリット事例をご紹介しました。
次回以降、ノウハウについて説明をいたします。
①このページは社内共有いただくことが可能です(外部への転送などはご遠慮ください)。
研究開発ガイドラインなどの資料はこちらからご請求ください。
②当社は以下のコンサルティングメニューを持っています。
興味をお持ちの方は、当社のセミナーをご受講いただくか、こちらから打ち合わせ依頼をご利用ください。
・R&Dマネジメントの社内セミナー(啓蒙目的)
・研究開発クリニック(診断)
・R&Dパイプライン構築のコンサル・研修
・潜在ニーズを解決する技術マーケのコンサル・研修
・定例アドバイザリ(R&Dマネジメントに関する助言・顧問的な立場から)
・ゾンビテーマの可視化、資源再配分
③関連するコラムはこちらからどうぞ。
