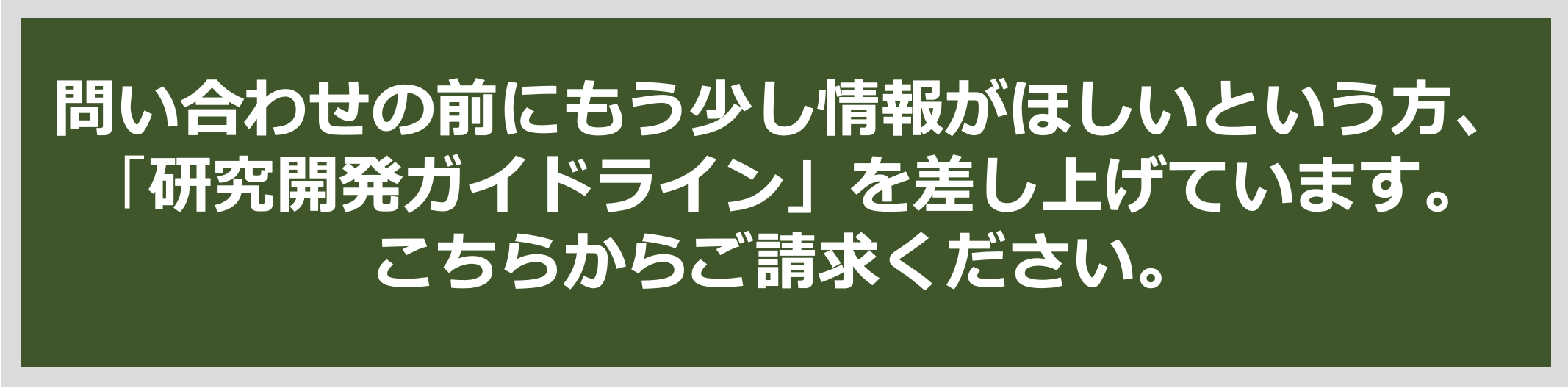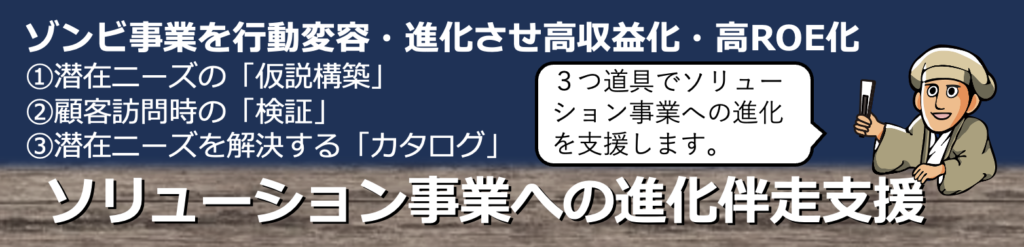
「顧客要望対応のテーマばかり、これって、うちだけの問題なのか?」
「顧客の調達部門にしか呼ばれないし、提案ができない(営業)」
「上流で提案したいが、顧客に図面やポンチ絵を示されて言いなりになる(営業)」
「営業が持ち帰る案件は、またカスタマイズ・小改善対応ばかり(開発)」
「顧客要望対応ばかりで、どうせこれまでと同じ(開発)」
「どうせ開発が実施してくれないから、ネタを持ち帰ろうと思わない(営業)」
このような悩みをもつ会社は少なくありません。技術営業が持ち帰る案件のほとんどが「顧客の要望に応える」ことが目的になっていませんか。本当は、もっと戦略的な技術開発を進めたいのに、日々の業務に追われてしまう。多くのR&D担当者や技術系の役員が、同じ悩みを抱えています。
この状況は何が問題なのでしょうか?
「潜在ニーズを発掘するように!」
責任者がこのように指示したとしても、現場は「潜在ニーズってどのように発掘すればいいんだ? 」と疑問を浮かべ、実際の行動変容にはつながりません。 責任者は潜在ニーズを発掘するべきだと言うことに気づいていますが、そのハウツーについて業務として具体化し現場に指示しているわけでは無いのです。そのために現場での行動変容が起こらず、営業は相変わらず顧客用語対応し、開発はそれに従って開発をする。そのため、小規模な改良案件が 開発テーマになってしまうのです。
では、技術営業の現場の行動変容を促すにはどうすればいいのでしょうか?
「現場の行動変容を実現し、潜在ニーズを発掘するための3つの条件」
営業と技術の連携が取れていないと、新規事業が生まれにくい状態が続いてしまいます。技術開発の優先順位が顧客要望に引っ張られ、「本当に価値のある技術」を生み出す機会を失うことになるからです。
では、どうすればこの状況を変えられるのでしょうか。答えは、技術開発のアプローチを顧客の「潜在ニーズ」に集約することです。そのためには、次の3つの条件を満たす必要があります。
1. 顧客の潜在ニーズの「仮説構築」をするために事前調査を行うこと
顧客が「欲しい」と言ったものを作るのではなく、顧客がまだ気づいていない課題を先回りして捉えることが重要です。そのためには、市場のデータや競合分析、過去の取引情報をもとに、技術開発の方向性を仮説として組み立てることが必要になります。
2. 顧客訪問時に潜在ニーズを「検証」し、R&Dに報告すること
営業が顧客の言葉をそのまま受け取るだけではなく、事前に構築した仮説をもとに、顧客と深い議論ができるようにすることが大切です。具体的な質問を投げかけ、課題の本質を見極めることで、技術開発に本当に価値のある情報をフィードバックできるようになります。
3. 潜在ニーズを解決する「カタログ」を活用して顧客と対話すること
技術の強みを、単なる製品のスペックではなく、顧客の課題解決につながる形で伝えられるようにすることが重要です。営業が「売り込み」ではなく、顧客と「共に課題を解決する」という視点で会話を進められるようにすることで、技術の価値が伝わりやすくなります。
しかし、これらの条件を満たすことは簡単ではありません。実際に取り組もうとしても、「営業と技術の連携が取れない」「社内の文化が変わらない」「どこから始めればいいのかわからない」といった課題に直面することが多いのではないでしょうか。
それでは、どうすればこの3つの条件を確実に満たし、技術と営業の連携を強化できるのでしょうか?
3つの条件を満たす「ソリューション事業への進化・伴走支援」とは?
単なる考え方の提示ではなく、技術と営業が連携し、継続的に新規事業を生み出せる仕組みを現場に定着させる支援プログラムです。
1. 「商談前準備」により、顧客潜在ニーズの仮説構築
商談前準備とは顧客に対するインテリジェンス活動のこと。初回訪問時、営業が商品を紹介するだけの状態から、「顧客の潜在課題を予測し、先回り提案できる」状態へと変わります。仮説を立てるスキルを組織全体で共有できるようになります。
2. 「潜在課題発掘シート」により潜在ニーズを検証・深堀りし、営業とR&Dで共有
単なるヒアリングではなく、「顧客の真の課題を明らかにする質問技術」を営業が習得します。その結果、技術開発に必要な市場情報が的確にフィードバックされ、開発の方向性が明確になります。
3. 「ソリューションカタログ」により顧客から声がかかる仕組みを構築
従来の「製品カタログ」とは異なり、顧客の課題解決を前提とした「ソリューションカタログ」を作成します。このカタログを使うことで、営業と顧客から潜在ニーズを引き出せるようになり、提案の成功率が大幅に向上します。
東証プライム上場企業で2000人以上の技術者・営業担当者が実践中
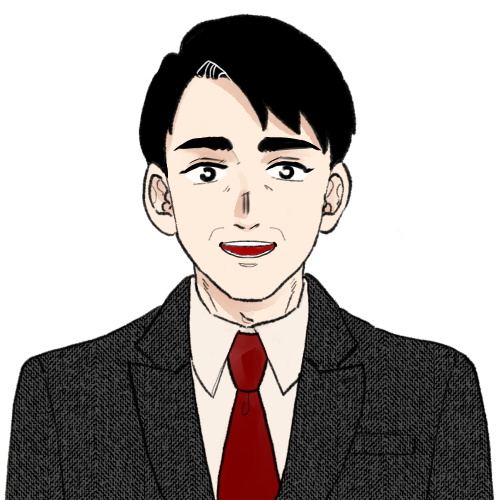
今まで必要と感じていながら忙しさにかまけて手を付けていなかった内容を、手法を含めて学ぶことが出来たのは大変有意義でした。半年間に渡りご指導いただきありがとうございました。掘り下げて検証するということが今まで不十分だったので、考え方や手法を学べたことは今後に活かしていきたいと思っています。これまで、ぼんやりと感じていた「F軸」について、意識して明確化することで既存の自社製品を再評価することにつながり、今後の資料(カタログ)作りに大いに活かせると感じました。
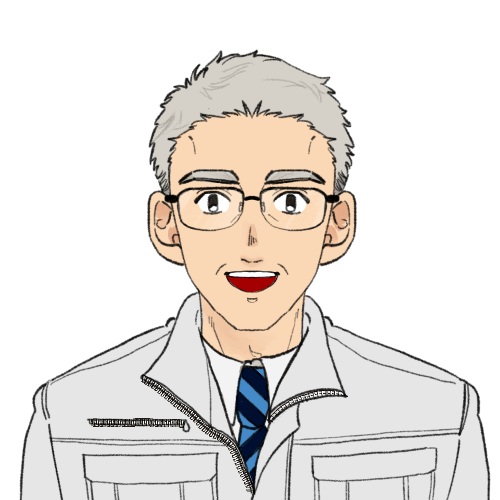
①商談前準備手法について
顧客課題情報を引き出す手法について学べた点が良かったです。顧客から引き合いがあった際に背景を顧客情報・特許などから予測することはありましたが、SLカタログ準備から顧客課題の把握、潜在ニーズ発掘シートへの落とし込みのような取り組みは行ったことがなく、顧客面談を通して課題を十分把握・引き出せているかと言えば、そうではなかったと感じています。顧客情報把握に加えSL履歴の棚卸し・SLカタログ作成など、慣れませんが実践していきたいと思います。
②潜在ニーズ発掘シートについて
研究サイドと情報共有する手法としてとても有効だと思いました。今まで単に顧客課題をまとめて共有することはありましたが、かなり薄い内容だったと感じています。良いシートを書くにしても顧客に頼られる存在になり、課題を相談してもらえるような関係性を構築する点が重要だと研修を通して学べましたので、商談前準備をしっかり取り組みたいと思います。
③SLカタログについて
製品カタログでなくSLのカタログとすることが重要であることが学べた点が良かったです。F軸を考えるトレーニングが不足していると感じています(今まであまりそういった考え方をしていなかったため)。今後活動する中で顧客にとって魅力ある(課題相談してもらいやすいような)SLカタログを準備できるように意識したいと思います。

研修期間中に研修でテーマアップをしていた製品を紹介プレゼンをする機会がありました。作成していたSLカタログをベースに説明し顧客の理解を得ることが出来ました。商談前準備手法は生成AIを活用し効率を図り、情報収集を目的とした訪問回数を減らすことができる。潜在ニーズ発掘シートへ落とし込み深堀をしてく重要性を得ることができました。
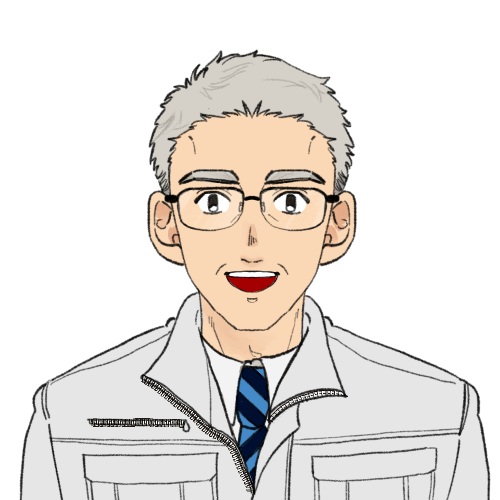
「技術マーケティングが“特別なもの”ではなく、日常の習慣になった」
「技術マーケは大事だと分かっていましたが、
実際には“営業がやること”という認識があり、
研究開発チームには根付いていませんでした。
しかし、3つのツールを取り入れたことで、技術者自身が“市場の視点”を持ち、
提案の精度が高くなってきたと感じます。
今では、技術マーケティングが日常の業務の一部になっています。」
① 商談前準備手法
商談前の準備として、過去の商談履歴の棚卸しを行い、典型的な課題とソリューションを整理する手法が明確に示されている点が良かった。特に、顧客の課題を事前に知り、解決策を持って商談に臨むことで、高単価商談の確率を上げる仕組みが整えられると感じた。また、情報収集・優先順位付け・詳細調査・標準提案書作成といった体系的なアプローチにより、営業活動の再現性と効果を高める工夫がされていると感じた。
② 潜在ニーズ発掘シート
単なる顕在ニーズではなく、顧客が自覚していない課題まで深掘りできる点が良かった。具体的には、過去の商談分析を基に「本来提供すべきだった理想の提案」を考えることで、顧客にとって最適なソリューションを導き出せたことであった。さらに、業界トレンドや工程分析を通じて、未来の課題を先取りする視点が盛り込まれている点も有益であると感じた。
③ SLカタログ
SLカタログを「顧客が営業を専門家として認識するためのツール」と位置づけている点が良いと感じた。特に、顧客に「この人なら課題を解決してくれそう」と思わせる設計になっており、信頼獲得の重要性が明確になっていると思う。また、単なる技術資料ではなく、事例を交えた分かりやすいフォーマットにすることで、顧客が相談しやすくなる工夫がされている点を良く感じた。
①商談前準備手法について、改めて自分の営業の方法について客観的に考える機会を得た事と、他の営業マンの対応方法や準備方法などを学ぶことが出来た。②潜在ニーズ発掘シートを作成する事によって、自分一人では気付けないような事を、具体的な質問を頂いて深堀りする事が出来たと思う。③製品カタログについても、改めて顧客目線で考える事と、F軸の考え方を用いて、自社製品の特長をより具体的にかつ効果的にカタログに落とし込む事の重要性を実感する事が出来た。顧客には伝わっていると考えていた事も、具体性やF軸となりうる特性をPR出来ていなければ、全く伝わっておらず、商談を進める機会を損失している可能性が感じられた。今後は商談に限らず、展示会の出展・展示にも活用する事の必要性を感じられた。
先ず弊社の営業活動(営業業務)におけるルール、仕組みがこれまで存在しておらず、全担当者からの引継ぎやOJTが全てで当たり前の感覚となっていた。
今回の研修を受けて、最も印象に残った言葉は「顧客の先生(医者)になる」という言葉で有り、顧客に指導、助言出来る存在になる事で携わる事業の付加価値や自分自身の存在価値を再認識出来るのだと時間しました。これまでも私自身が携わっている繊維事業において、顧客の先生になる事を意識し先生に成り得る為の知識や経験の習得に努めていたが、それが当たり前と感じていた為、自信を持つ事が出来ていなかった。今後も顧客の先生になる為に必要な情報の収集、知識の習得に努めていきたいと感じました。
①商談前準備手法について
時間が無いとの理由で、これまで引き合いを頂いた顧客へのヒアリングによる情報収集をスタートラインと捉えていましたが、今回の研修で商談は1回のみで顧客訪問前の準備が重要であると認識出来ました。生成AIについてもこれまで全く使用した事が無かったため興味を持つ事が出来、今回の研修をきっかけに外部セミナーも受講し、効率的な情報収集の1つの方法として使える事を認識出来ました。直ぐに1回の商談で完結出来るような力量までは身についていませんが、1回の商談で完結させる意識を持ちながら商談前の準備を行う事を継続していきたいと思います。
②潜在課題発掘シートについて
弊社がこれまで使用していた資料として、製品開発に落とし込む開発計画書とその前に営業から研究へ開発を依頼する開発依頼シートが存在しており、今回の潜在課題発掘シートは営業から研究へ発信する開発依頼シートに近いものと感じました。ただ、従来の開発依頼シートは営業の主観が入っている要素が多かったのですが、今回の潜在課題発掘シートの方が主観で無く根拠や業界共通の課題を解決可能な説得力有るシートで構成されており、今後活用出来ると判断しております。
③SLカタログについて
今回の研修で私自身は作成していませんが、営業担当が作成したカタログに対するコメントやブラッシュアップする為の必要情報の伝達等についてはある程度行えた為、作成のイメージは出来ております。
①商談前準備手法について、改めて自分の営業の方法について客観的に考える機会を得た事と、他の営業マンの対応方法や準備方法などを学ぶことが出来た。②潜在ニーズ発掘シートを作成する事によって、自分一人では気付けないような事を、具体的な質問を頂いて深堀りする事が出来たと思う。③製品カタログについても、改めて顧客目線で考える事と、F軸の考え方を用いて、自社製品の特長をより具体的にかつ効果的にカタログに落とし込む事の重要性を実感する事が出来た。顧客には伝わっていると考えていた事も、具体性やF軸となりうる特性をPR出来ていなければ、全く伝わっておらず、商談を進める機会を損失している可能性が感じられた。今後は商談に限らず、展示会の出展・展示にも活用する事の必要性を感じられた。
進め方(全体で最短2ヶ月、標準7ヶ月)
初回打ち合わせにおいてプログラムの内容についてご説明をいたします。狙い効果他社事例等をご説明いたします。貴社の目的に沿うようであれば実施の詳細についてお伝えいたします。
契約やNDAはその後結ぶこととなります。
① ソリューション履歴の棚卸しと言うワークシートに基づいて過去の商談を振り返っていただきます。
② また、それに基づいて、自社のソリューションを抽象化し、高度化を行ってカタログとして見せられる状態にしていただきます。
① 商談前準備と言う顧客訪問前の準備を徹底して行うための情報収集を行っていただきます。
② 商談前準備に基づいて想定される顧客課題を解決するためのソリューションを考案していただきます。また想定した課題が生じているかを確認するための質問事項等も準備します。
実際に商談に行った後に作成する潜在課題発掘シートと言うものを作成します。潜在課題発掘シートとは、顧客の潜在課題を発掘するために作成する帳票です。
研修参加者(技術者、営業)が技術部門、営業部門の責任者に対して実施した内容を業務として実施するための提案する形式で報告会を行います。業務改善の提案なので、 原稿現状の業務を分析し、どこをどのように改善することで、技術マーケティングの3つ道具をインストールできるかを提案してもらいます。
まずはお気軽にご相談ください
「興味はあるけれど、すぐに導入を決めるのは不安…」という方のために、無料相談・オンライン説明会 を開催しています。技術と営業の連携を強化する方法や、具体的な成功事例をご紹介しながら、貴社にとって最適な進め方をご提案いたします。
📌 無料相談・オンライン説明会の進め方例
✅ 貴社の課題に合わせた個別相談(30分)
- 技術と営業の連携がうまくいかない要因を分析し、具体的な改善策をご提案します。
- 実際に導入した企業がどのように変化したのか、事例を交えてお話しします。
✅ 「技術マーケティングの実装・伴走支援」プログラムのご説明(15分)
- なぜ技術と営業が分断されてしまうのか、その原因を解説。
- 「仮説構築→検証→カタログで対話」というフレームワークの具体的な活用方法をご紹介します。
✅ 質疑応答(15分)
- 参加者の疑問にその場でお答えしながら、導入のイメージを明確にしていただけます。