当社セミナーにご参加いただきありがとうございました。
本ページは、株式会社如水のセミナーにご参加いただいた方向けのFAQです。
個別相談しようか迷っている方へ
個別相談はいつでも可能ですので、このページの連絡先にご連絡ください。
コンサルティングや研修をご検討中の方へ
個別相談と同様に、ご連絡ください。
社員数30人の中小企業です。セミナーで提案されたやり方は大企業のやり方に思えますが、中小企業での事例はどうですか?(経営者の方)
技術プラットフォームを取りまとめたり、技術カタログを実際に作成することは大企業でしかできないかもしれません。しかし、顧客の潜在課題を発掘したりすることは普遍的で中小企業でも適用できます。
材料メーカーや、金属加工業、プラスチック成形業などの中小企業でも同じ考え方で研究開発や営業ができている事例があります。
すべての場合にうまくいくかは分かりませんが、うまくフィットすると良い結果が出ると言えます。
テーマ創出活動にはそれなりに時間をかける必要があると思いますが、
どの程度の時間をかけるべきものでしょうか。
ケースバイケースですが、概ね一つのテーマを仕上げるのに、48時間から96時間程度を目安にしております。上記は技術マーケティング研修でのテーマ創出に要する時間で、初めて実施する場合に要する時間です。
専任者の組織を置いても、兼任の担当者を置いてもそれほど要する時間は変わらないと思いますが、慣れれば短い時間でできると思います。
研究開発や営業については分かったのですが、人事制度についてどう考えればいいでしょうか?(経営者からのご質問)
セミナーでは人事制度について時間を割いていませんが、極めて重要です。
特に、MBO(目標管理制度)で設定する目標がどのようなものかで社員の行動は変わります。また、面談の頻度が極めて重要です。
技術経営に関するリーダーシップ理論では、以下が重要であるとされています。
- ビジョンの設定
- ゆるいマネジメント・目標設定
- 楽しい仕事の設計
- 余裕を生み出す
- 頻繁な面談の実施
特にミドル(部課長)が変わることが非常に大事ですが、ミドルを変えるのは経営者です。詳しくは個別相談でお尋ねください。
当社では、コーチングやリーダーシップの研修と仕組み導入を通じた改善を支援しています。
潜在課題を発掘するために、営業部門の意識を高めたいのですが、どうすればいいですか?(研究開発部の方のご質問)
セミナーでもお話した「潜在課題発掘ツール」を営業部門に導入するのが一番の近道です。
運用と共に意識は代わり、有用情報が入るようになります。
担当役員同士に話をして連携していただくと、強い連携の仕組みが作れます。
意識を高める最初のステップは、会社全体のイノベーションの仕組みを説明する社内セミナーを営業部門と共同で実施することが一つの案です。
詳しくは個別相談でお尋ねください。
社内セミナーについてはこちらをご覧ください。
知財マップを作っていますが、新しいテーマに繋がりません。どうすればいいでしょうか?(知財部の方のご質問)
①まずは知財情報を正しく使えているか、考える必要があります。
以下の流れで分析をされているでしょうか?(例えば材料メーカーであれば以下のようになります)
ステップ1.技術の棚卸し
↓
ステップ2.アプリケーションマップを作成する
↓
ステップ3.お客様の開発動向(関連分野の分析)
ニーズマップ(潜在課題マップ)を作成する
↓
ステップ4.競合の技術動向調査
参考となるコラムを記載します。参考になさってください。
②知財情報を正しく使っていてそれでも出ないということであれば、新しい軸を作り出す必要があります。
新しい軸の作り方は、潜在課題によるもの、ユーザー調査によるもの、積年の課題によるものなど、いくつかの方法があります。
新規テーマの立案を知財部門のリードで実施する場合でも、臆することなく、新しい軸の必要性を主張していただきたいと思います。
新しい研究開発テーマを設定する場合は、コア技術と繋がりのあるテーマであるべき、という理解でよろしいでしょうか?
確かに、コア技術とつながりがあればベターです。
しかし、必ずしもそうではないケースもありますし、コア技術との繋がりがないからと言って早期に排除すべきではありません。
当社は材料メーカーです。技術棚卸は各素材がどういう用途に使われているという程度の物しかありません。それは棚卸になっているのでしょうか?
なっていません。セミナーでもご説明したとおり、棚卸ししただけでは何も起こりません。棚卸しの目的が必ずあるはずです。その目的の一つは新規テーマの設定です。
どのような用途があるかの明確化は有益ですが、用途情報は、新テーマを設定するのに不足があります。新テーマを設定するには、自社の技術を展開できるように把握しなければなりません。
特許情報は公開情報のため、顕在化した課題ともいえます。ヒアリングシートや特許検索のほかに、有効な潜在課題発掘方法があれば、教えて頂けませんでしょうか。
いくらか手法があります。その一つが、ユーザー評価系を作ることです。
例えば、ソニーが自動車(VISION-Sというコンセプトカー)を作りましたが、これは自動車メーカーの課題を浮き彫りにするためです。ソニーからすれば、自動車メーカーの潜在課題を発掘するためであり、これを「ユーザー評価系を作ること」と表現しています。
ユーザー評価系を作るのは、潜在課題発掘の非常に大きなポイントです。できるだけ、ユーザーと同じことができることが大事です。
他にも手法はありますが、手法はともかく、発掘がうまくいくかどうかは、他所よりも早く実施できるかどうかが大切だと思います。早ければ意味がありますが、競合と同じスピードでしている限りは意味はありません。
用途探索で、市場がニッチすぎて市場規模が予測できないケースがよくあります。どう予測すればいいでしょうか?(研究開発部門のご質問)
大きなマーケットでは市場予想がありますが、小さい市場の場合、市場予測がある方が珍しいと思います。
そのような場合、フェルミ推定しかありません。より大きな市場から合理的に予想することです。例えば、エンジンの市場規模を考える時、自動車の世界市場が9000万台だとして、エンジン搭載の割合が90%であれば8100万台となります。自動車用エンジンは8100万台、部品も同じだけ生産されます。
分解するのも大事です。エンジンは、自動車用だけでなく、発電用、船舶用、作業車両用もあります。分解されたものごとに合理的に推定することです。
研究開発部門からIPランドスケープの依頼が来るようにしたいですが、どうすればいいでしょうか?(知財部の方のご質問)
現場レベルでの提案活動をすることをおすすめしています。
知財部門は開発部門の会議(知財との連絡会ではなく研究開発部門の会議)に出ているでしょうか?出ているのであれば、面白い技術シーズが見つかった場合に「用途探索してみない?」と言ってみたり、商品が成熟して検討しているテーマがつまらないように見える場合に「差異化の軸を見つけてみない?」などと提案することです。
事例やマップを示しながら話すと必ず興味を持ってくれますので、その準備をすることをおすすめします。
知財部門が開発部門の会議に出ていない場合には、出ることから始めたほうが良いです。技術者が知財部門に依頼しようと思うのは、通常、相当遅いです。
知財部門の方で「技術者がテーマを創出する必要性や技術戦略を作らせる必要性」をお感じの方には、社内セミナーがベターです。
社内セミナーについてはこちらをご覧ください。
ヒアリングシートについてもっと詳しく教えて下さい。
セミナーでは、潜在課題を発掘するためのヒアリングシートを提案しています。
セミナーでは3項目のヒアリングシートをお示ししていますが、併せて「実際に企業で導入すると5ー15項目程度になる」という話をしています。
項目数が3から5や15に増える理由は、その会社なりの現実があるからです。現実とは、業種特有の用語を反映したり、業種特有の背景情報の掴み方を反映したりする必要があります。また、営業社員の理解力もあります。
ブルーオーシャンとは、自ら潜在課題から創出した市場なのでしょうか?
ブルーオーシャンを生み出す手法としてバリューイノベーションが知られています。これは既存の顧客価値を弱め、今無い顧客価値を提供するものです。
事例として、「俺のフレンチ」のようなスタンディングレストランや、サウスウェスト航空、Wii(任天堂のゲーム機)などの事例が知られています。
上記がバリューイノベーションで考案されたものだとは思いませんが、俺のフレンチは「安くて美味しいものを食べたい」という顧客価値を伸ばし、他方で「座れる」という顧客価値を削ったもので、バリューイノベーションの説明には合っています。
サービス業・飲食店などでは、顧客価値を列挙できるのでバリューイノベーションは比較的容易かと思いますが、BtoBなどの業種ではなかなか顧客価値を発掘できないと思います。
むしろ潜在課題の発掘に目を向けるべきだと考えており、それがブルーオーシャンにつながることは間違いありません。
営業部門のトップにも話を聞かせたいのですが、可能ですか?
営業トップの方に当社セミナーにご来場いただくのも良いのですが、
営業部門と研究開発部門の共同で、「成熟メーカーのイノベーションの仕組み」というタイトルの社内セミナーを実施することが良いと思います。
誰でも参加自由として、多くの方に聞いていただくと、営業部門、経営、研究開発の連携が必要なのだという意識は必ず醸成できます。
社内セミナーについてはこちらをどうぞ。
ステージゲートの運用のコツはあるのですか?(研究開発部門の方のご質問)
セミナーでもお話しましたが、整備はできていても運用が伴っていないことが多いです。
逆に、整備ができていなくても運用がうまい(研究開発テーマの進捗がスムーズ)会社はあります。
正直に言いますと、運用が全てと言っても過言ではありません。
- ステージゲートの書面に記載された事項の要件は何なのか?
- 要件が記載されていると判断できるか?
- 要件にないようなことでも儲かるような検討がなされているのか?
文字にすると、上記のようなことを検討していくのですが、運用する人のレベルが伴わないと、きちんと運用できたことにはならないです。
運用をする人は、事業化に成功した方で、競争優位性の源泉をよく見極める方が良いです。おごらず、パワハラなどがないことも重要です。
個別相談はいつでも利用できるのですか?
過去に、セミナーにご受講頂いた方であれば、いつでも利用可能です。
個別面談について、上司と相談した上で決めるでよろしいでしょうか。
過去に、セミナーにご受講頂いた方であれば、上司の方とご相談の上で結構です。
また、同席いただいても構いません。
当社は経営の考え方が変わりません。どうすればいいでしょうか?(社員の方の質問)
経営者の考え方は会社の根幹なので、大事にすべきだと思います。
経営者の考え方が変わらなければ、セミナーで提案したようなことも実行できません。
諦めるのではなく、経営者に「新しい考え方・情報を提供します」と前置きしてセミナーでお伝えした考え方をお伝え下さい。
また、当社で提供している社内セミナーを実施するのも一手です。
「外部講師の社内セミナーを行います」ということで、参加自由とすると経営者から社員まで気軽です。
こうした社内セミナーにより変革した事例は多数あります。
セミナーで使用した用語について
TRIZ=発明的問題解決理論のことです。
DB=データベースのことです。
MI=マテリアルインフォマティクスのことです。
知財DD=知財デューデリジェンスのことです。
講師の連絡先を教えて下さい。
こちらにご連絡ください。
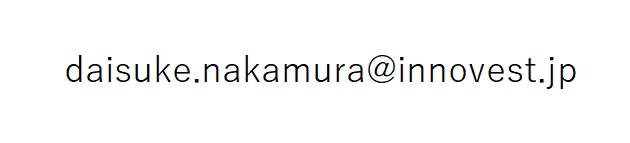
知財部門は開発部門の下請け的な仕事が多いと考えます。知財部門から開発/マーケット部門に対してテーマ出しをさせ、研究開発をさせるには、体制から考える必要があると思いますが、どのような組織体系が好ましいか例を挙げてお教えください。
まず、知財部と研究開発部の対等な関係からだと思います。体制はその後かと思われます。単なる権利化部署であれば、事務処理部署と化してしまいますから、研究開発部門かみれば、知財の専門性を感じても、付加価値を感じないと思います。
付加価値とは、権利化以上の仕事であって、例えば、テーマだしの促進などです。知財部が提案型にならなければ、研究開発も「やってみよう」とは思えないので、テーマ出しに至る道筋を提案する必要があります。そのような提案・利用・効果、提案・利用・効果の積み重ねがあって初めて、付加価値となり、対等な関係ができるのではないでしょうか?
既知課題である知財情報から新規課題、新規構成を創出する「先読み取り」は大変難しいではないかと思います。
何か具体的な手法があれば、ぜひご指導お願いいたします。
難しいと思われると思いますが、可能です。ただ、知財情報偏重は意味をなしませんので、注意が必要です。非知財情報が多く必要なので、その点はご留意ください。知財部にいると、非知財情報を使ってはいけないように思いますが、そんなことはありません。どんどん活用することです。非知財情報も含めて考えることで、顧客課題の先取りはできます。
テーマ企画書のとりまとめ、投資判断に関して、複数研究所を有し、かつ事業部制の企業の場合、その投資判断は事業部の意向が強くなりがちかと思いますが、判断基準の設定や、その意思決定方法に関して教えて下さい。他社様の課題やそれに対する解決策等あればそれらの情報もお願いします。
判断基準に関しましては、競争優位性のあるテーマなのか、技術的な課題はなにか、顧客課題は明確か、どのように技術調達していくのか、どのように事業化していくのか、など
ステージに応じていくつかの審査項目があるべきかと
存じます。
他社での課題は、上記設定をしていてもうまく審査できないことだろうと思われ、判断者の属人性や属人性の排除というのは永遠の課題かと思います。
ただ言えるのは、事業化に成功したことのない方で合議制をするよりも、事業化に成功したことのある方の独断と偏見の方が成功すると思います。
テーマ企画書に関して顧客の動向等記載すべき事項は理解しますが、特に素材開発を主とする川上企業(BtoB)では、末端までいくつも顧客があるテーマの場合、顧客の顧客の動向も計画書に記載すべきでしょうか?その場合どう盛り込めば良いでしょうか?(特にテーマによって、末端までの顧客数が異なるかと思います)
顧客の顧客の動向は、把握しなければ潜在課題発掘にならないことが多いと思われます。
潜在課題発掘マニュアルでもお示ししておりますが、顧客の顧客やエンドユーザーの動向を見ておくのは必須です。
