
知財部の変革と「IPアーキテクト」育成の必要性
IPアーキテクトとは
知財部員が本社のデスクにとどまり、研究開発現場との連携が十分に取れていないのではないかと感じたことはありませんか。
また、発明提案書を受けて出願を進める受け身の知財活動に対して、「もっと上流から関わるべきではないか」と疑問を持ったことはありませんか。
従来、知的財産部門の主な役割は、技術者から提出された発明提案書をもとに特許出願を行い、いわゆる「守りの特許」を形成することにありました。実際、多くの企業では発明提案の受付、先行技術調査、特許事務所への依頼という流れを中心とした業務が長年続けられてきました。
知財を取り巻く事業環境の変化
しかし、近年の事業環境では、競合他社が異なる技術方式で自社技術を回避して市場に参入したり、他社が先に特許を取得して自社に警告を発するような事例が増えています。その結果、守りの特許だけでは競争優位の確保に限界があることが広く認識されつつあります。
こうした背景のもと、知財戦略に対する社会的な要請も変化しています。たとえば、東京証券取引所はコーポレートガバナンス・コードにおいて、知的財産や無形資産に関する戦略的な開示を求めており、また経済産業省や内閣府知的財産戦略本部からも、ROICを重視した経営の観点から、知財の「取得」ではなく「活用・価値創出」に向けた変革が強く推奨されています。
このように、知財部門にはこれまでの「守る役割」から一歩踏み出し、研究開発の上流から事業戦略と連携して「攻めの特許」を設計・形成することが求められています。言い換えれば、技術開発における競争力の源泉を、知財の力で事前に確保していくことが新たな使命となっているのです。
とはいえ、研究開発の初期段階から攻めの知財を設計し、戦略的に特許権を取得できる人材は、これまで十分に育成されてきませんでした。その課題を解決する新しいアプローチとして登場したのが、「IPアーキテクト」という考え方です。
IPアーキテクトとは何か
IPアーキテクトとは、従来の知財リエゾン担当のように、単に特許事務所との橋渡しを担うのではなく、研究開発の初期段階から参画し、事業戦略と知財戦略の融合を実現する存在です。
たとえば、次のような力を備える人材です。
- 守りの特許だけでなく、将来の市場構造を見越して攻めの特許を構想する力
- 技術者との共創を通じて、知財戦略を具体的な研究テーマに落とし込む力
- 上位概念化・下位概念化の視点で発明の位置づけを設計する力
こうした力を持つ人材こそ、企業のROIC向上に貢献する、次世代の知財専門職なのです。
攻めの知財とは何か
攻めの知財とは、市場における優位性を獲得・維持するための戦略的な知的財産のことを指します。詳しくはこちら。
- 研究テーマの立案段階から関与し、技術をどのように囲い込むかという視点でクレーム設計を行う
- 他社の参入を阻止し、仮に参入してきた場合でも模倣困難な技術構造を事前に構築する
- 守るだけでなく、競合に対する牽制力・交渉力を持つポジションを形成する
このような設計思想に基づく知財活動が、「攻めの知財」です。
守りの知財とは何か
一方で、守りの知財は自社技術の模倣を防止することを目的とした従来型の知財活動です。詳しくはこちら。発明提案書に基づく特許出願、製品化された技術の囲い込み、ライセンス・訴訟対応などが主な内容となります。
これらは依然として重要ではあるものの、事後的かつ限定的な対応であるため、長期的な競争優位の構築には不十分であるといえます。
攻めの知財を生み出す7つのステップ
本研修では、攻めの知財を設計するための体系的な思考法として、以下の7つのステップを学びます。
- 発明の把握
技術的課題とその解決方法を正確に整理します。 - 上位概念化
発明を抽象化し、応用領域や技術的広がりを捉えます。 - 下位概念化
構成要素に分解し、要素技術の精度を高めます。 - 下位概念を実現する代替技術の列挙
技術的選択肢を整理し、競争力ある構成を見出します。 - 実施例の列挙
応用例を広く想定し、特許の守備範囲を拡大します。 - 発明群の階層化
コア技術、周辺技術、用途展開を明確に整理します。 - 競合技術の検討
競合他社の出願傾向や技術動向を分析し、差別化戦略を立案します。
このようなステップを習得し、研究開発と知財の橋渡しを担う人材こそが、これからの企業に求められるIPアーキテクトです。
研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます
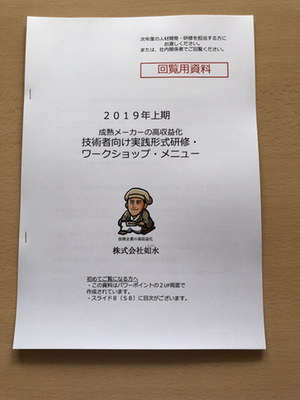
研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。
部署内でご回覧いただくことが可能です。
しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。
ご安心ください。
・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?
・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?
・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?
・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?
・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?
・新規事業化の体制構築を進めるには?
・最小で最大効果を得るための知財教育とは?
