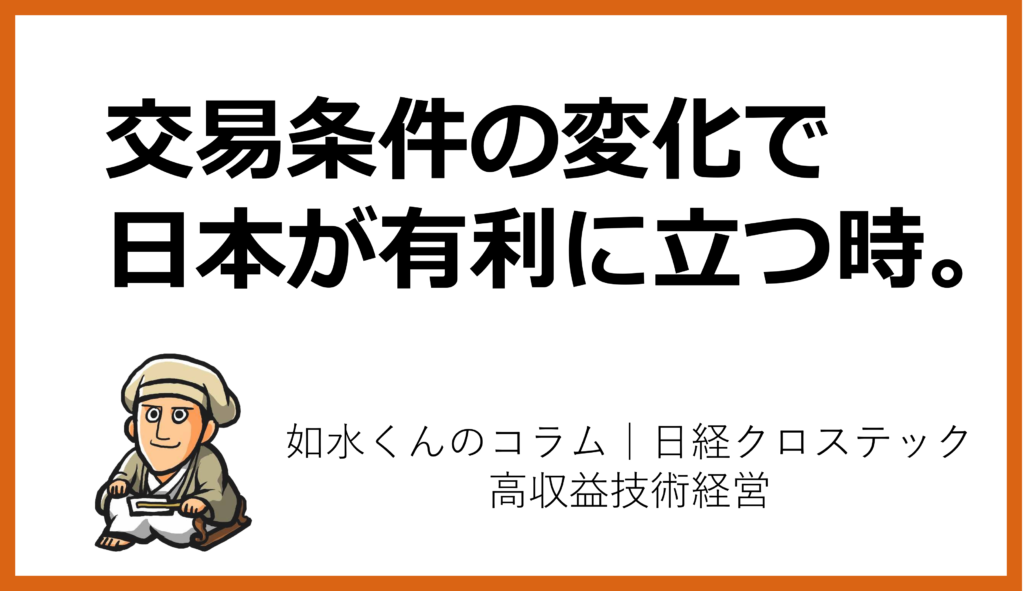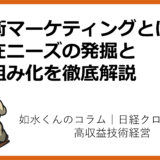筆者の住んでいる京都ではEVのタクシーが多くなった。目につくのはもちろん海外製。Hyundai、BYDといったところだ。中国メーカーによるEVの高性能化や低価格化がニュースになっており、特に筆者の目につくのはBYDの高性能・低価格の車のニュースだ。
現在、BYDをはじめとする中国EVと同じ価格水準で同じ性能の車を作る事は日本のメーカーには難しいのだろう。実際、日産が苦境に陥っているのは周知のとおりだ。推測になるが、ホンダとSONYが共同開発したAFEELA(EV)も高額で競争にならないのではないか。他の日本のメーカーも同様の経営環境がある以上、苦境に陥るのではないかという予想を持つ読者も多いのではないだろうか。
今日のコラムでは、筆者の独断と推測で日本の自動車メーカーの今後の経営環境について占っていきたい。日経クロステックで掲載される以上、日本のメーカーの今後を支配するのは何と言っても「技術が大事」、と言いたい所だが、技術よりも大事なものがあると思わざるを得ない。それは交易条件だ。
交易条件を理解するのに、中国メーカーの躍進が参考になる。今の中国メーカーの勢いは続くのだろうか?足元の中国メーカーの躍進の背景にどのような前提条件があったのだろうか?中国メーカー躍進の背景には中国が享受してきたメリットを指摘せざるを得ないだろう。
2001年に中国がWTOに加盟したことによって、中国の特に輸出におけるメリットは大きく拡大した。新自由主義的な国際貿易体制のもと、中国は大量のものを有利な交易条件(関税が安くかつ元安)で輸出することによって経済を成り立たせてきたし、近年では自動車を輸出することによってそのメリットを享受し続けてきた。
トランプトレード
しかし、これが大きく変わろうとしている。知っての通り、トランプ大統領の関税を始めとする保護主義だ。足元では、日本のような同盟国やカナダやメキシコのような隣国にでも関税をかける動きがよく聞かれる。この動きには米国でインフレを招くなどの指摘が多く限界があるため継続には疑問が残るものの、保護主義が米国民の意思ともみられることから長引くことが予想される。
米国は中国にも輸入制限を課している。中国からの輸出入制限には安全保障上の強い理由があり、強いデメリットがあっても継続するだろう。ウクライナやガザでの紛争でサプライチェーンの強化が話題になっている所、BRICS諸国との輸出入は最小限にする必要性があるからだ。
トランプ大統領は、一期目こそ風変わりな大統領と見られていたかもしれないが、二期目の当選を迎え米国民の意思表示と見ることが妥当ではないかと思われる。すなわち自由貿易主義で安い輸入品を受け入れると言うこれまでの体制が関税などを駆使して輸出入を自国で自国が有利になるように制御することが米国民の意思となったのだ。
そして注目すべきは同様の動きが西欧諸国にも見られることだ。西欧諸国はEUでまとまろうとするなど多国間強調主義を取ってきたが、右派政党が台頭していることに見られるように自国主義に変化しようしている。報道によれば独仏の右派政党は関税での保護主義を主張している。こうした動きは継続し、トランプ大統領のような自国主義をさらに強調するリーダーが現れ、貿易ルールを自国に有利に持っていこうとする動きが強まるのではないか。
足元では観測されないものの、今後は西欧諸国からも関税が発動される可能性は高まっているし、それは、これまで貿易メリットを享受してきた中国車に対する輸入規制が含まれるだろうと想像される。つまり、中国はこれまで享受してきた交易条件で、市場の大きな西欧諸国に輸出するというメリットを享受できなくなるのではないか。
このようにして欧米への市場のアクセスが制限される中国メーカーは、欧米市場の代わりにBRICS市場へ供給されることになるだろう。また、西欧でもBRICSでもないアジア・アフリカ諸国では保護主義の台頭が見られないことから、中国メーカーは制限を受けない。こうした市場では世界中の自動車メーカーが熾烈な競争を繰り広げることになるだろう。
一方、欧米の自動車メーカーは、対抗関税等の輸入規制により現在のような交易条件での中国ビジネスを失う可能性がある(現時点では、技術的にすでに敗北しつつあると見ることもできる)。
日本のメーカーは?
では、日本のメーカーはいかなる制限を受けるのだろうか?日本では今のところ保護主義を取ろうとする政治的主張は強くないと思われる。これが変わらないとすれば、日本の自動車メーカーは中国市場には変わらずアクセスできることになるし、逆に日本国内でも中国車との競争になることになる。将来的にも、日本は西欧諸国と異なり、中国とは人的・距離的に遠くないため、中国を関税で排除することは考えにくいのではないだろうか。
一方、欧米諸国からは関税を課されるなどのリスクは残るものの、西側の一員ともみなされうる日本はサプライチェーン強化の一環から関税は課されたとしても低く抑えられる希望がある。
以上をまとめると、日本のメーカーは米国、欧州のアクセスが一定程度制限される可能性があるが中国メーカーに比較すれば制限は軽微であり、中国の市場にはこれまで通りアクセスできることになる。同様にBRICS諸国も市場にできるだろう。
そうすると、日本メーカーは、他国のメーカー特に中国メーカーよりも交易上の制限を受けづらいという解釈が可能だ。つまり、世界中の自動車メーカーが交易条件の変化により制限を受ける中で、日本のメーカーはそうした条件の変化による制限を受けづらく、比較的自由に輸出入が可能だということである。こうした変化により、今後、日本のメーカーに利があると見るのが妥当ではないだろうか。
ただし、もちろん市場が広ければ勝てるという甘いものではない。次回のコラムでは、日本の自動車メーカーが世界市場で勝つための方法論について展望したい。
研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます
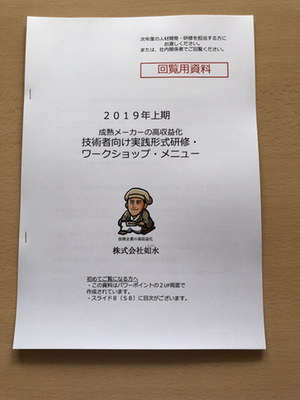
研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。
部署内でご回覧いただくことが可能です。
しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。
ご安心ください。
・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?
・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?
・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?
・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?
・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?
・新規事業化の体制構築を進めるには?
・最小で最大効果を得るための知財教育とは?