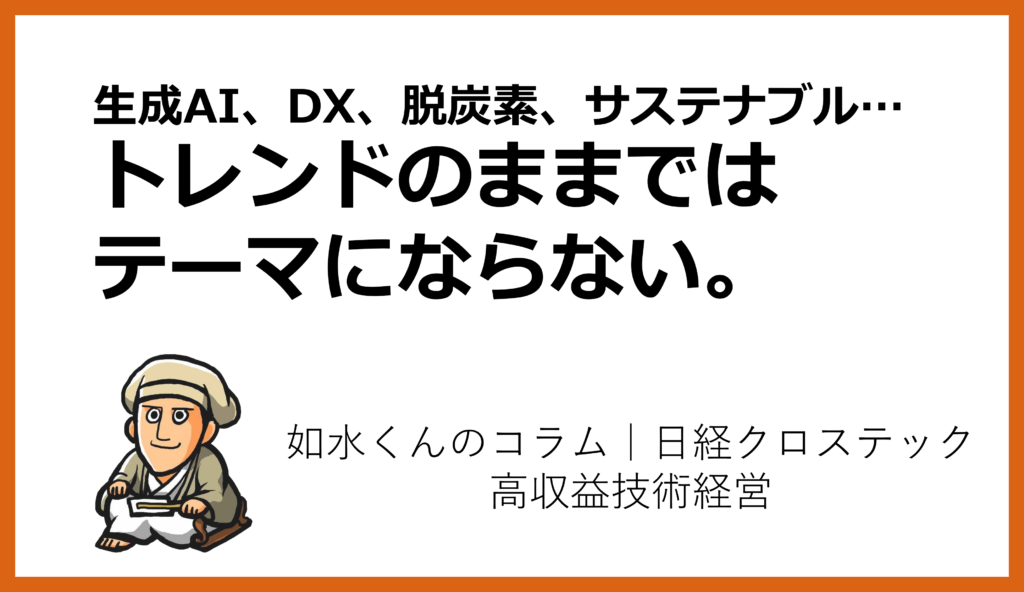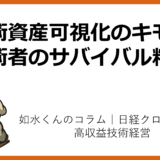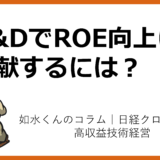「ありがとうございます。これで先に進めそうです。」とAさんは笑顔を見せてくれました。私はその言葉に胸を撫で下ろしながらも、彼のテーマの進捗状況をじっくりと聞くことにしました。Aさんはメーカーの若手社員で、生成AIという最先端技術の研究開発テーマに取り組んでいるところです。
壮大な開発ロードマップで感じられる熱量
Aさんのテーマは、いわゆる生成AIの開発というものでした。彼の計画はとても壮大で、生成AIアプリケーションを事業化するというものでした。開発ロードマップもすでに壮大に描かれており、その熱量と意欲には、私もつい「なるほど、素晴らしいですね」と声をかけずにはいられませんでした。Aさんが生き生きと語る姿は、若いということの特権を存分に感じさせ、私の心にも清々しさをもたらしました。
話をお聞きしつつも、私は一方で指摘しなければならないことがあると感じていました。それは、最先端技術のままでは研究開発テーマにはならないということです。Aさんの壮大なテーマは、確かに先端技術に触れておくという意味では良いかも知れません。しかし、それがそのままでは、企業の研究テーマやビジネステーマとして実行に移すのは難しいのです。
どうしたらテーマになるのか?
私はAさんに、研究開発テーマを創出する上で大切なこととして、以下のポイントを伝えました。まず、最先端技術をそのままテーマ化してはいけないということです。テーマとして形にするためには、必ず具体的な顧客課題を具体的に特定する必要があります。
顧客課題とは、現在の顧客が抱えている具体的な問題でも、将来の顧客が抱えるであろう課題でも構いません。ですが、顧客課題として具体化されていなければ、せっかくの技術もビジネスに結びつきにくく、社内でのテーマ承認も得られにくくなるのです。
社会課題のママではテーマにならない
私はAさんの生成AIテーマをその視点で眺めました。生成AIは確かに世の中で大きな注目を集める技術です。社会課題としても重要です。しかし、Aさんの計画をそのまま見たとき、「どの顧客のどの課題をどのように解決するのか」という視点が具体化されていないように感じました。生成AIの開発そのものが目標になってしまい、顧客課題の解決につながっていないのです。
私はAさんに尋ねました。「このテーマを実際に社内で実行できるようにしたいですよね?」と。Aさんは少し戸惑いながらも「はい、もちろんです」と答えました。続けて「社内でこのことを話したことがありますか?」と聞くと、Aさんは急に表情を曇らせ、「はい、話したことはありますが……あまり受け入れてもらえませんでした」と言いました。その言葉から、Aさん自身がなぜ受け入れられなかったのかが分かっていないように感じました。
先端技術のママでもテーマにならない
そこで私は、「このテーマを社内で受け入れてもらえるようにするためのノウハウを一緒に考えましょう。そしてまず、先端技術のままでは研究テーマにはならないんですよ」と伝えました。Aさんはまだ飲み込めていないような表情でした。私はさらに続けました。
「生成AIの開発は、確かに素晴らしいテーマです。ただ、生成AIという分野そのものは、今やビッグテックや日本のスタートアップなど多くの企業が既に手がけています。基盤となる生成AIの開発自体はある程度進んでいる状況です。だからこそ、Aさんが取り組むべきは単に生成AIを作ることではなく、その生成AIを活用して『どの顧客のどの課題をどのように解決するのか』という視点でテーマを組み立てることなんです。」
顧客課題への具体化を
「確かにその通りですね」とAさんは素直にうなずいてくれました。私はさらに続けました。「そうであれば、自社事業で役立ちそうな場面を想定して、生成AIの顧客課題解決のシーンを作ってみませんか?具体的には、顧客の業務を一つひとつ洗い出し、その中で生成AIがどのように使えるのか、どのような成果を出せるのかをストーリーとしてまとめてみるんです。その上で、その課題解決が本当に価値のあるものかどうかをディスカッションペーパーにまとめ、実際に顧客と話し合ってみる。それによって、社内でも外でも納得してもらえるテーマになるはずです。」
Aさんは少し緊張したような顔を見せながらも、「これで顧客のところに行けそうです」と笑顔を取り戻しました。その言葉を聞いて、私は本当に安心しました。大きなテーマを掲げることは大切ですが、それを現実のものとして動かしていくには、やはり顧客課題への落とし込みという地道な作業が必要なのだと改めて感じたのです。
打ち合わせが終わったあと、私はAさんの背中を見送りながら思いました。若い技術者が挑戦するテーマには夢があります。しかし、その夢を実現するためには、先端技術を顧客課題にまで具体化し、社内外で納得してもらえるようにストーリーとしてまとめる力が必要です。それこそが、せっかくのチャレンジを促進し、技術者の挑戦をサポートするための大切な一歩なのだと感じました。
研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます
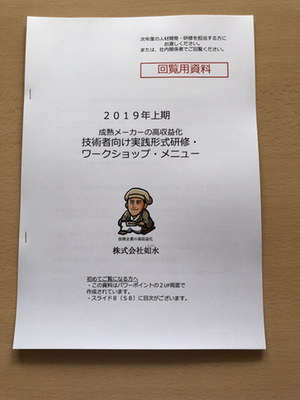
研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。
部署内でご回覧いただくことが可能です。
しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。
ご安心ください。
・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?
・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?
・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?
・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?
・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?
・新規事業化の体制構築を進めるには?
・最小で最大効果を得るための知財教育とは?