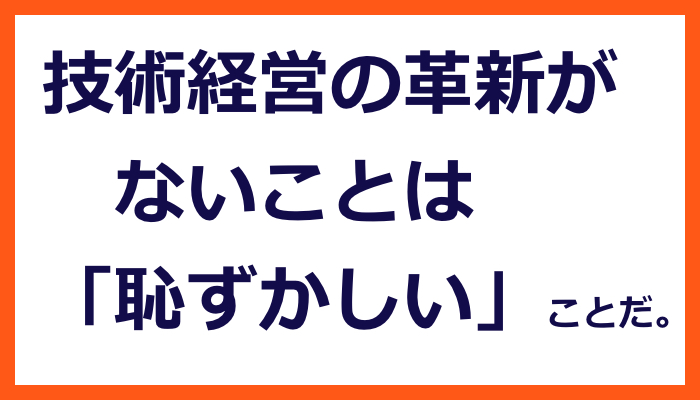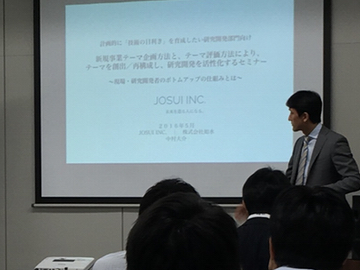NHK大河ドラマ「真田丸」、いよいよ佳境に入り、舞台は大阪城に移りました。ご存じの通り、真田幸村(信繁)は豊臣方の一員として大阪城に入城して活動を始めます。
大阪城に入城した武将たちを観察すると、豊臣方の勝利を信じて疑わないのはほとんど幸村のみと言っていいでしょう。後藤又兵衛は「(大阪城に)死に場所を求めて来た」、毛利勝永は「自分の腕を試したい」とする、それぞれ設定です。上司に当たる豊臣秀頼は決断が出来ず、最後は淀殿の「鶴の一声」で全てが決まってしまいます。
戦略の決定会合を描いているシーンでは、幸村は「打って出る」ことを献策します。作戦の詳細を述べて先手必勝を提案するものでした。しかし幸村以外の全員は、その動機にはいろいろあれど、「籠城」策を献言。幸村の策は完全に奇策扱いとなりました。
淀殿の一声で籠城が決まった後、次は城の弱点である南側に出城を作る作戦を発案しましたが、これも奇策と見られ、後藤又兵衛以外の賛同者は得られませんでした。後に、その効果が明らかになり妙策だったことが判明するわけですが、周囲に賛同者がおらず孤立する幸村の立場や心理が描かれていました。
翻ってこのシーン、まるでどこかの会社で研究開発テーマの事業化に苦しむエンジニアの姿を見ているようでした(笑)。支援者はいない。策を唱えるのは自分一人か少数の仲間のみ。上司は決断力に乏しく、最後は院政をひく影の権力者の一声で潰される――。
ご承知の通り、豊臣方は大阪の陣で滅びてしまいますが、同じく会社がそんな状況だと潰れてしまいますよね。有名な企業の中にもそういう会社は、実は少なくないと思います。皆さんの会社はいかがでしょうか? 例えば、こんなケースがあります。
研究させてもらえないんです
とある会社でコンサルティングのインタビューをしていた時の話をご紹介しましょう。私は過去の成功事例をヒアリングすることにより、成功事例を起こしやすくするための示唆を得るようにしています。その時も、成功事例を幾つか眺めながらインタビューをしていました。
中村「この成功事例は誰の技術シーズだったのですか?」
担当者「これは中途採用者のものなんです。その社員は、『今の会社では研究させてもらえないので…』と言って転職してきたんですが、当社に入って研究を継続してみると(たまたま)当たりましてね。以前の会社で発案していたようなのですが、どういう理由かその会社ではやらなかったようなんです」
その成功事例は、売上や利益の規模としては決して大きなものではありませんでしたが、利益率としては十分すぎるほど高く、高収益商品に育っているということでした。
上述の中途採用者を仮に「Aさん」としましょう。Aさんは、自分が発案した研究テーマを愛していたと思います。しかし、転職前の会社ではどういうわけか研究をさせてもらえない。予算がつかない。そうした状況でも、Aさんはたとえアングラでも研究ができていればその会社に留まっていたかもしれませんし、周りにAさんのテーマを理解してくれる人がいれば慰められたかもしれません。しかし、おそらくそうではなかったのでしょう。周りに理解者や支援者がいない状況は、どんな人でも辛い。Aさんも、例外ではなかったと思います。
それにしても、転職前の会社はどういう理由でAさんに研究をさせなかったのでしょうか、とても興味があるところです。なぜなら、Aさんのやる気を削いだだけではなく、Aさんと保有技術をみすみす他社に渡してしまったのですから。とはいえ、そこに合理的な意思があれば、それはそれで良いのです。その上で、Aさんも会社の指示の下、お役立ち度が高くて高収益な研究開発ができるのであれば、きっとやる気が出たはずです。
がしかし、Aさんは転職を選びました。会社には合理的な意思が見られず、会社の指示する研究をしていれば見込みがないと判断したからに違いありません。もし本当にそうだとすれば、転職前の会社は危機的な状況、まさに大阪の陣が始まる前の大阪城内のような環境だったと言えます。
今求められているのは「技術経営3.0」
大河ドラマでも描かれていますが、大阪城内は淀殿を中心とする権力構造があり、意思決定が合理的とはとても言い難い状況でした。こんな大阪城しかり、組織が外部環境の変化についていけないのは今も昔も変わりません。Aさんの転職前の会社も、合理的な意思決定ができなかったと言わざるを得ません。
「組織は戦略に従う」は経営学における有名な格言ですが、多くの会社では「戦略が組織に従っている」逆の状態になっています。Aさんの転職前の会社では、おそらく組織や仕事のやり方を支配するパラダイムが一世代古かったに違いありません。
高度成長期、日本が追いつき追い越せの時代には、社員に我慢を強いてキャッチアップ型の研究開発をすることで日本は戦後復興に成功。その後、バブル景気を迎え、中央研究所にも潤沢に予算が回るようになりました。研究開発テーマを自由に作って自由に研究する――。これを「技術経営1.0」と呼びましょう。
しかしバブルが崩壊すると、少子高齢化の問題もクローズアップされ「失われた20年」が到来します。ここで企業の中では管理統制が行き届くようになり、短期的でスグに成果に結びつくようなテーマしか研究開発できなくなってしまいました。これを「技術経営2.0」とします。
そして失われた20年の後、すなわちここ5年くらいの間は、管理統制だけでは短期的な成果は出せても中長期的な成果は出せないことに気づき始めます。ところが、です。組織構造や業務のやり方が全く変わっていない。Aさんの転職前の会社も含め、そんな会社が実に多いのです。
今求められているのは「技術経営3.0」というべき、新しい技術経営のパラダイムです。具体的には、中長期的なテーマを仕込みつつ、短期的なテーマをスピーディーに刈り取るというもの。とりわけ、前者の視点が必要とされています。中長期のテーマを仕込むという業務のやり方は、会社によってマチマチですが、方法論があります。その方法論に従って若手や中堅が実践可能な状態を創り出していくことこそが、現代の経営者には強く求められています。
知財経営も革新が必要
技術経営と知財経営は一体不可分――。技術経営を革新するならば、知財経営も革新する必要があるというのが、私の持論です。そこで、技術経営1.0~3.0にならって、知財経営1.0~3.0を定義してみましょう。
知財経営1.0:実施する事業の形態のみ知財を取得して事業を保護していた時代。このパラダイムは、後発の競合他社が別方式を考案して知財侵害なく事業を模倣することで葬り去られました。
知財経営2.0:実施する事業の形態以外にも競合他社が実施する形態も含めて知財化を行い、事業を保護しようとした時代。このパラダイムはしばらく機能し、業界が安定している時代には非常に奏功しました。
知財経営3.0:代替品によって事業そのものが置き換えられる時代。これが現在です。典型が、フィーチャーフォンの知財を多数保有して実施していた事業がスマートフォンによってガラリと置き換えられたケース。ここで求められるのが、「代替品の脅威」に備えた研究開発ということになります。
とはいえ、そうやすやすと代替品の研究開発に資源を投入できないことは歴史が証明しています(詳細は、ハーバード・ビジネス・スクールのクレイトン・クリステンセン教授の著作『イノベーションの最終解』などをご参照ください)。ならば、どうするか。研究開発の上流、しかも超上流でビジネスと知財の視点で知恵を出し尽くすことです。研究開発の企画段階に知財部門が関与する、研究開発者の知財能力を高くするなど、いろいろなアプローチの仕方はありますが、詰まるところ、超上流でいかに知財発想を持ち込んだ研究開発の企画を行うかという点が重要になります。
加えて、権利行使を十分に意識した権利取得を行うことが必要です。これまでは、権利行使を意識しない企業が日本には多かったと思います。そもそも日本は事を荒立てず穏便に済ませるお国柄ですから、仕方がありません。しかし今は、そうは言っていられない時代です。巧妙な模倣に対して断固とした権利行使が出来るようにするためには、権利行使を真剣に意識した明細書の作成が不可欠です。残念ながら、権利行使を真剣に意識した明細書の作成が出来ている会社はまだまだ少数と言わざるを得ません。
次世代に渡すのが恥ずかしい
さて、先述の、私がインタビューした方の話に戻しましょう。この方は一緒に仕事をする中で、古いパラダイムを脱して技術経営モデル・知財経営モデルの革新を続けるべく努力をしていました。そんな彼がインタビューの締めくくりに漏らした次の一言が、私の胸に刺さりました。
「こんな(組織の)状態では、次世代に渡すのが恥ずかしい」
彼の所属する会社では彼をはじめとする幹部の努力の甲斐あって、技術経営2.0まで革新されていました。しかし彼自身、まだまだ道半ばだと感じていて、先の一言につながったのです。私は、幹部とはこんな心境なのかということをリアルに知って感じ入り、これこそまさに「ノブレスオブリジェ(高貴な者の義務)」だと思ったことを記憶しています。
こんな幹部の下で働ける人は幸せですね。だからこそ、件のAさんも本来の実力を発揮し、高収益商品の開発につながったのではないかと思います。時代が変わっても、組織の問題が最終的には人とか意識とかの問題に帰結するのは変わらないのかもしれません。
歴史に「たられば」は禁物ですが、大阪城にも、こんな心境の上層部がいたら良かったのかもしれないなと、豊臣贔屓(ひいき)の人間としては思ってしまいます。いつの世も、幹部は持続性のある組織の発展を俯瞰していなければいけませんね。