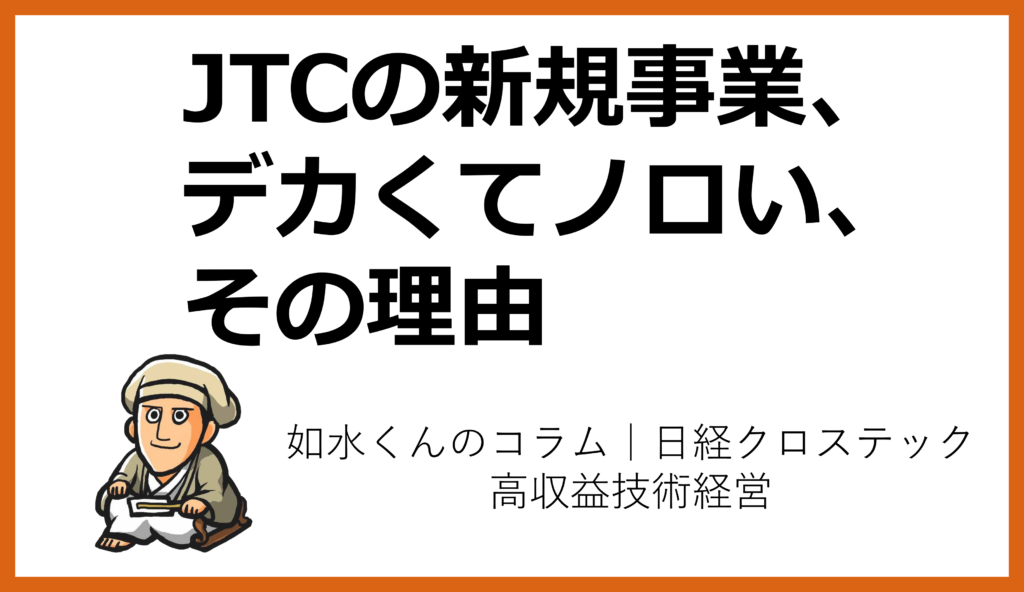「『ターゲット市場が小さい』と役員に言われてしまいました。どうしたら良いでしょうか?」と相談をしてきたのはA社で新規事業開発を担当するAさんだった。数年前のこと。場所はA社の会議室。Aさんの表情は若干虚ろに見えたのを記憶している。戸惑いが入り混じっていたようにも見えた。
Aさんの話を聞いた所、Aさんが担当するのは、会社が長年培ってきた技術のうち、新規事業に活用可能だと判断されたもの。Aさんはその技術を使って新しい用途を考案し、新しい用途における需要をインタビュー等で具体化したそうだ。実際の顧客になりそうな人にもインタビューでき 具体的なニーズをつかんでいるのが好印象だった。
企画内容はどうだったか?Aさんの企画書を見たところ、技術の内容だけでなく、顧客の需要、需要と技術の適合性、競合調査、競合との相違点など明確にされていて、新規事業企画として良い調査がなされていた。 競合調査の結果、競合がいたので競合よりも早く始めることが要件だと思われた。「なぜすぐに実施しないんだろうか」と疑問に思ったことを記憶している。
事情を聞くと、Aさんが新規事業開発の社内提案会でこの提案をしたところ、参加した役員から「ターゲット市場が小さい」と言う指摘をもらったということだった。「そうかな」と私はここでも疑問を感じたものの、この指摘は解消しなければ始められないという意味のものだったという。前述の通り競合もいたのでスピード勝負なのに開始が延期になっている状態に、私は第三者でありながら危機感を覚えた。
延期が続く理由
Aさんは「延期が何度も続いている」とも言う。提案しては細かなところを指摘され、修正する時間が与えられるのはいいが、小さな指摘と修正によってスタート時期が遅くなるという意味でもあった。そのことにはAさん自身も苛立ちを覚えていたらしい。「どれぐらい延期が続いてるのですか?」とお話を聞いたところ、「1年は続いている」とのことだった。
私が「どんな場なのですか?」と聞いた所、「役員勢揃いなので、一言一言が重たくてコメントというよりも事実上の指示になってしまいます。ちょっとした批判のようなものでも直さなくてはならなくなって、開催頻度もあって半年とか1年とか時間が経過してしまいます」 Aさんは不満気味に答えた。
私はAさんの表情にピンときた。 よくあるJTC病だなと思ったのだ。どういうことかと言えば、日本の会社は2010年代半ばから新規事業開発に取り組み始めた。具体的には新規事業開発部署を新設し、そこに技術者を集めた。当然ながら新規事業開発部門にはその部門のルールが必要だ。多くの場合、コンサル会社がルール策定を依頼され、コンサル会社の提案する通りにルールが決まっていった。
そのルールの1つがステージゲートだった。ステージゲートとはR&Dで活用されるフレームワークの1つで、新規事業の進捗管理手法だ。それ自体は悪いものではないものの、この時導入されたステージゲートは、失敗がないようにという意図で作成したものだった。失敗がないということは、要するに「重箱の隅をつつく」ということだ。そのため、技術者が新規事業開発をやりやすいと感じるものではなかった。導入時点で誰もこのことに気づいていなかった。
失敗しないようにするためには、多くの役員・関係者が出て審査することにもなる。ようするに「大勢で寄って集って(たかって)重箱の隅をつつく」のだ。審査に多くの役員が参加すれば意思決定が遅くなるのはイメージしやすいところだろう。そして、彼らは審査に貢献しようとするがゆえに、「何か問題点を指摘しなければならない」という心理が働く。その結果、大企業で働いてきた役員だけに「既存事業に比較した市場規模の小ささ」を指摘するのは自然だ。Aさんのテーマはその指摘に遭った。
新規事業に「既存事業に比較して十分なサイズの市場規模があること」を要件とするというのはどういうことなのだろうか?一見至極まともに見えるかもしれないし。しかし、新規事業担当者の視点では全く異なる。
わかりやすく野球に例えてみよう。おそらく、「すべての打者にホームランを求める監督」のようなものだろう。確かにホームランは試合の流れを変えるし好ましい。しかし、誰にでも打てるわけではない。「自分にはバントしかできません」という選手から見れば、監督の要求は無理筋に思えるだろう。
現実として野球ではヒットやバントでランナーを出し、地道に得点を重ねることも重要だ。同じように、新規事業も最初から大ヒットを狙うのではなく、小さな市場で試行し、成長させながら大きな市場へ展開していくのがセオリーと言える。
例えは下手で申し訳ないが、「既存事業に比較して十分なサイズの市場規模があること」がいかに愚かな要件かをご理解いただけたのではないか。失敗のないようにという動機で導入されたステージゲートのもと、善意のお偉方が勢揃いでコメントを述べるのだから、そもそもホームランはおろかバントしか打てない新規事業開発担当者は凹むのだ。Aさんの表情の裏もご理解いただけると思う。
JTCの新規事業
あなたの会社でも新規事業に取り組んでいるのではないだろうか?そしてその新規事業開発部門は拡大しているだろうか縮小しているだろうか?縮小している会社も多いだろう。なぜかと言うと結果が出ないからだ。
結果が出ない理由の一つは、上に書いた通り、ステージゲートと現場の不整合にあることも多い。野球において選手と監督の相性が悪ければチームの成績が振るわないのと同じで、会社の性質とステージゲートが合わなければ新規事業も結果が出ないのだ。
会社の性質に合わせて制度を変える必要があるのに、ステージゲートと言う制度は、コンサル会社からもらった型紙のまんまと言うのはどう考えてもおかしい。そしてその結果が出ないことを社員に押し付けるのはもっとおかしい。
野球ならば監督を変えてパフォーマンスが大きく変わる事は日常茶飯事だ。新規事業でも同じだ。制度を変えてパフォーマンスが変わる事はよくある。それなのに制度を変えずに結果が出ないことを社員に押し付ける仕組みの愚かしさにいい加減に気づくべきである。
研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます
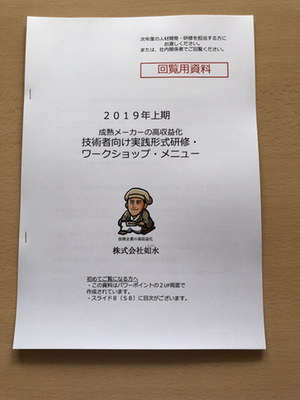
研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。
部署内でご回覧いただくことが可能です。
しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。
ご安心ください。
・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?
・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?
・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?
・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?
・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?
・新規事業化の体制構築を進めるには?
・最小で最大効果を得るための知財教育とは?