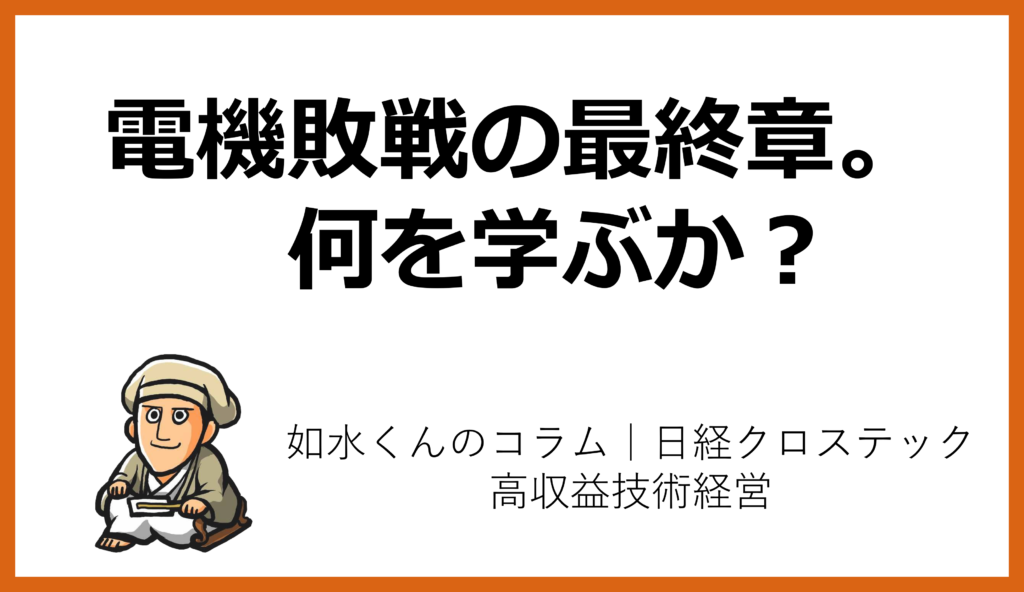電機敗戦の30年
パイオニアが台湾企業に買収されることになった。1980年代や90年代に消費者として同社の製品を経験した40代以降の方なら、パイオニアがどのような会社だったかご存じだろう。オーディオビジュアルというジャンルで一定の存在感があり、現在はカーナビのメーカーとして知られているものの、かつてはオーディオ専用機器である「コンポ」を作るメーカーとして一般消費者に非常に有名な会社だった。そのパイオニアが台湾企業の傘下に入ることになったのだ。
KENWOOD(2008年に日本ビクターと経営統合)、SANSUI(山水電気、2014年破産)とともに、高いブランドイメージを誇った同社だが、いわゆる「失われた30年」の間に三社ともすっかり元気をなくしてしまった。大手電機メーカーの凋落と比べれば小さなニュースに見えるかもしれないが、「またか」と思った読者も多いのではないだろうか。
かつてオーディオビジュアル機器は、家電量販店の売り場の大きな部分を占めていた。例えばCDラジカセやコンポである。CDやMDが珍しかった頃、それを録音・再生できる機能を備えた商品は非常に魅力的だった。では、今その売り場は何に変わっているのだろうか。
実際に家電量販店に行ってみると、従来のオーディオビジュアル機器(ラジカセやコンポ類)は売り場の片隅に追いやられ、その隣に大きなスペースを占めているのがイヤホンやヘッドホン売り場だ。その売り場を眺めてみると、日本のメーカーで存在感を放っているのはソニーくらいで、それ以外はBOSEなどの高額ブランドを除けば、中国を含むアジアの新興ブランドが多いように見える。
パイオニアはもともとオーディオ機器のメーカーであったため、イヤホンやヘッドホンを作ることは技術的に可能だったはずだが、デジタル時代の家電量販店の売り場での競争力確保には失敗したようだ。
こうした状況について従来、メディアを中心に「電機の敗戦」と表現し「マネジメントの失敗」と総括してきた。実際、日本企業のマネジメントが一時期成功し、その成功モデルが通じなくなってきたことは明らかだし、それは正しい。電機敗戦の最終段階にある今、異なる角度から「電機の敗戦」を考察してみたい。
その角度とは、マネジメントとは反対の技術者(働き手)の視点だ。働く側、すなわち技術者側の視点から「電機の敗戦」を見てみたい。我々技術者は電機の敗戦を起こしたくて起こしたわけではない。頑張ってもダメだったのだ。働き手の視点では、電機敗戦の30年間、何があったのだろうか?
働き手視点での電機敗戦
1.高い説明責任がモチベーションを削いできた
まず挙げたいのは、新しい企画の立案時に課される説明責任だ。どんなに意欲のある技術者でも、会社の仕組みの中で動かなければならない。審査制度では「売上は上がるのか」「利益は出るのか」「技術的に可能なのか」と問われる。
高い説明責任を課されると、技術者は萎縮せざるを得ない。「利益が上がると説明できる範囲」「技術的に説明できる範囲」と上司に問われるのを考えると、どうしても保守的で既存領域にとどまるテーマを企画してしまう。
また、上長が理解できるレベルのテーマしか生まれない。こうした仕組みや、上長の理解できる範囲の狭さを前提とすれば、既存事業の枠を超える提案は出てこなくなってしまうのだ。技術者にとって、そんな30年間だったのではないだろうか?
2.新しいテーマで成功しても出世できるか分からない
次に挙げたいのは、新しいテーマで成功しても出世につながるかどうか分からないという点である。大企業であればあるほど、組織は固定的になりやすい。長年にわたり固定化すれば、いわゆる出世ルートや出世レースもまた固定化した競争となりがちだ。
既存事業で実績を上げることと、リスクを取って新しいテーマを打ち出すことのどちらが有利かと問われれば、多くの人は確実に成果を残せる既存事業での実績を選びたくなるのは当然だ。
3.働かないおじさんが周囲のモチベーションを下げる
三つ目に挙げたいのは、「働かないおじさん」問題である。日本企業に「働かないおじさん」が存在するのは、すでに広く知られた話になってしまった。解雇されることはないため会社には居続けるが、目立った成果を上げることもない。おじさん本人からすれば「どんなにサボってもクビにならない」という安心感があるが、周囲の技術者からすれば「働かないおじさんと同じ待遇しか得られない」という失望感につながる。
どんなにリスクを取って挑戦しても、働かないおじさんと待遇が大きく変わらない現実を見せつけられれば、挑戦する意欲は失われてしまう。「ここで成果を上げるより、転職しよう」というモチベーションになってもおかしくはない。過去30年間の転職サービスの盛り上がりにはこうした背景もあるだろう。
今後、どうするか?
「電機敗戦の30年」が終わりを迎えた今、どう変化しているのだろうか?
まず会社について。大きく変化を遂げてモチベーションを上げることに大きく成功した会社がある一方で、30年前とほとんど変わらない会社もまだあるというのが現実だ。
一方で個人を取り巻く環境は大きく変わったのではないだろうか?30年前は上司が変えられないのが当たり前だったが、今は上司も評価される。個人はより強く会社に縛られていたが、今は転職が当たり前の時代になっている。働かないおじさんは今も減っていないが、人手不足の影響も強く若手の給料は上がっている。
要するに、30年前から考えると個人を取り巻く環境は大きく変わっていると言って良いと思う。自社の仕組みを変えなければ会社が淘汰されるようになってきているからだ。
そのため、個人としてはやりたいことを思い切りやればいい時代になっていると思う。もし、やりたいことができなければその会社を去れば良い社会環境(転職環境)は整っている。
さて、電機敗戦時代も終焉。淘汰や買収されるくらい時価総額が下がってくるということは、利益が出せていないことの裏返しだ。働き手がやりたいことができず、上司の理解できる範囲内での仕事しかできていない会社である証拠だろう。会社は個人がもっと輝ける環境を提供する必要があるし、個人はもっと自分を輝かせる努力が必要だ。
研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます
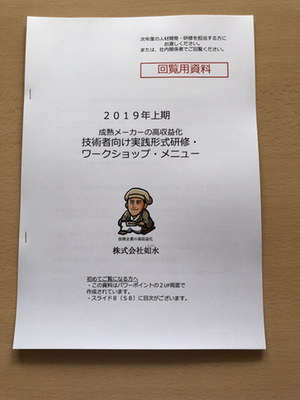
研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。
部署内でご回覧いただくことが可能です。
しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。
ご安心ください。
・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?
・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?
・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?
・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?
・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?
・新規事業化の体制構築を進めるには?
・最小で最大効果を得るための知財教育とは?