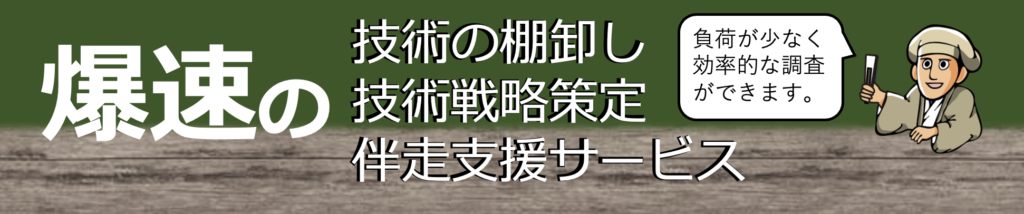以下に示す経済産業省、東京証券取引所および内閣府による各種ガイドライン等の発出を受け、知的財産を所管する責任者(知財部長)は、いまや自社における知財マネジメントの高度化を強く迫られております。
従来、知的財産のマネジメント高度化に対する関心は、競合他社からの権利行使や係争など、具体的なリスクが顕在化した場合にのみ生じるものであり、未然の戦略的対応としての知財経営が重視されることは稀でありました。しかしながら、東京証券取引所による上場企業改革の流れを受け、ROE向上を重視する経営姿勢が広く浸透しつつあり、その文脈の中で知財部門も例外とはされず、経営貢献が明確に問われる時代へと移行しております。
現在、知財部門に求められているのは、自社のビジネスの価格決定権に積極的に関わること、マネジメント体制、ガバナンス状況等の積極的な開示、さらには他社にとっても参考となるベストプラクティスの提示であります。すでに先行する企業群においては、いわゆる「攻めの知財」の一環として、事業戦略と連動した特許取得による市場優位性の確保等の事例が開示されており、そのような概念を持たぬ企業にとっては、競争上の遅れを感じさせる内容ともなっております。
本稿では、そうした外部環境を踏まえ、知財部門の責任者がいかにして自社の知財マネジメントを高度化できるかについて論じました。知財の在り方は企業ごとに千差万別であり、その実践には多様な努力と工夫が求められますが、本稿が読者の皆様にとって、知財戦略の視座を広げる一助となれば幸いに存じます。
東京証券取引所「コーポレートガバナンス・コード」(2021年改訂)
改訂されたガバナンス・コードでは、企業に対してサステナビリティに関する方針と具体的な取り組みの開示を求めています。知財部門の責任者も、研究開発やイノベーション活動と連動する形で、知財をどのように活用し、競争優位や中長期の利益に結びつけているかを明確に説明することが期待されています。これは、非財務情報を通じて投資家との建設的な対話を行うための土台となります。
内閣府「知財・無形資産に関する投資家向けガイドライン」(2023年)
このガイドラインでは、投資家が企業の無形資産活用力を理解しやすくするために、企業側が何をどう説明すべきかの視点が示されています。知財部門の責任者は、知財の活用プロセスや価値創出の仕組みを定量的・定性的に整理し、開示資料に反映させることが求められています。また、知財に関するKPIの導入や、知財戦略の妥当性を経営視点で説明できるスキルも重視されています。知財部門が投資家との対話において重要な役割を果たす時代になってきています。
経済産業省・特許庁「企業成長の道筋~投資家との対話の質を高める知財・無形資産の開示~」(2025年)
このガイドラインでは、知財部門の責任者に対して、知的財産を企業価値創造の中核と位置づけ、経営戦略と一体となった知財戦略を構築することが求められています。また、経営層や取締役会との対話を通じて、知財の活用状況や将来的な収益への貢献について説明できる体制を整えることが重要とされています。従来の出願・管理中心の役割から一歩踏み出し、企業の持続的成長に貢献する「攻めの知財経営」への転換が求められております。
知財マネジメントでROEを向上するお役立ち記事
知財戦略とIPランドスケープ、攻めの知財形成
知財戦略とはなにか?知財戦略とはIPランドスケープ、攻めの知財形成のこと。ROEやROICを向上させる方法を解説します。
ROIC経営のもと、IPランドスケープをどのように実行し、開示するのか?
IPランドスケープは攻めと守りの知財形成と共に重要な活動です。ROIC経営のもと、IPLをどのように実施するのか、その概要を説明いたします。
攻めの特許と守りの知財で価格主導権を上げるには?
価格支配に必要な知財は攻めと守りの知財。攻めと守りの知財とはなにか?その取得方法について解説しています。知財マネジメント高度化の核となる内容です。
権利形成の観点から研究開発計画に関わるIPアーキテクト
IPアーキテクトとは、単なるリエゾンではなく、研究開発の初期段階から参画し、攻めと守りの知財を取るように技術者に提案、高い参入障壁を築く職務です。
政府等が求める知財マネジメントと開示内容、把握していますか?
東京証券取引所や内閣府等が示す指針において、知財マネジメントをどのように実行及び開示することが求められているのか、その概要を説明いたします。
知的財産報告書などで、具体的に企業が知財マネジメント等について開始している例から、具体的な商品や特許の説明を伴う開示事例について取り上げています。