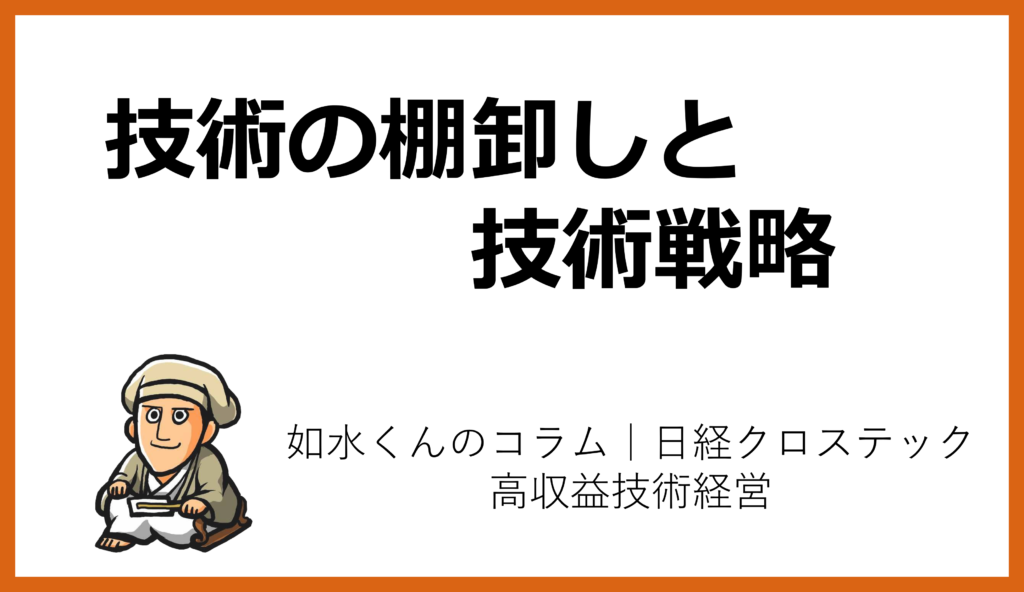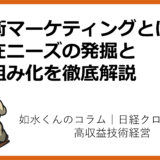技術の棚卸しに関して、当社によく寄せられるご相談は、たとえばこんなものです。
「ウェブ情報を参考に技術の棚卸しを試してみたのですが、これでよいでしょうか?」
そう言って、作成途中のExcelシートなどを見せてくださいます。

よくあるご質問は、記載の詳しさや粒度についてです。
「このくらいのレベルで大丈夫でしょうか?」
「もっと書くべき項目はありますか?」
そんな問いかけに対して、私がお伝えしているのは「そもそも、この作業に時間をかける必要はありません」ということです。
技術一覧表を作ることにどのような意味が?
棚卸しの作業、つまり技術一覧表を整えること自体には、大きな意味がないのです。
なぜなら、技術棚卸しは経理の棚卸しとは違い、リストができても成果物にはならないからです。
経理なら、棚卸しを通じて決算書という明確なアウトプットが生まれます。
しかし、技術棚卸しの場合は、「一覧表ができたね」で終わってしまうことがほとんどです。
技術の棚卸しの本当の目的は?
では、本当の目的は何でしょうか?
それは、社内に眠る技術を活かして、新しい技術や商品、研究開発テーマを生み出すことにあります。
にもかかわらず、多くの企業では、一覧表づくりに時間をかけすぎてしまい、肝心のテーマ創出にたどり着けないのです。
さらに問題なのは、「誰がテーマを作るのか」が曖昧な点です。一般的に、棚卸しのフォーマット作成はコーポレートの技術戦略部が行い、記入作業は事業部の技術者が担います。
ところが、テーマを生み出す主体がはっきり決まっていないため、コーポレートは「事業部が作るべきだ」と考え、事業部は「戦略部からテーマが降りてくるはずだ」と思っている――そんなズレが起きています。
しかも事業部は、日々の業務に追われて新しいテーマどころではないのが実情です。
何がしたいのか?何ができるのか?
こうして、技術棚卸しだけ(一覧表の作成作業)が1年、2年とかかり、中途半端なExcelシートを前にして「これでいいですか?」と私のところに相談に来られる、という流れが非常に多いのです。
そのとき、私がお聞きするのは、「ところで、御社は何をしたいのですか?」という問いです。
すると、多くの方が言葉に詰まってしまいます。
技術棚卸しをやれと言われて始めたものの、その先をどうするかは考えられていなかった――そんなケースがほとんどです。
そのような状況は察せられますので、こちらから「棚卸しをもとに、新しい技術開発テーマを作りたいのですか?」と尋ねると、「ああ、そうです」とうなずかれる方が多いのですが、
そもそも「技術の棚卸し」という言葉自体がしっかり定義されておらず、
棚卸し後に何をするべきか、明確なイメージを持っている方が少ないと感じます。
棚卸しの本当の意義は、リストを作ることではありません。
そこから独自の技術開発テーマを作り出すことにあります。
そして、その作業主体を「事業部なのか」「技術戦略部なのか」、まずは明確にすることが重要です。
テーマ創出を誰が担う?
テーマ創出は、どちらが担っても構いません。
大事なのは、会社として方針を定めることです。
たとえば、事業部で既存テーマへのリソースを減らし、新テーマに時間を割く体制を整える方法もあります。あるいは、コーポレートの技術戦略部に人材を集め、事業部を支援する形でテーマを作る道もあります。
どちらも正解です。ただし、実態としては、技術戦略部が事業部を支援しながらテーマ提案を行う形に落ち着くことが多いのが現実です。既存の組織形態を維持しながら(事業部長の権限を認めながら)、全社横断的な技術開発案件を実施するためには、コーポレート技術戦略部門は提案しかできないからです。
ただし、この場合も、新たな問題が立ちはだかります。せっかくコーポレート技術戦略部門が技術の棚卸し結果を有効活用して提案しても、事業部が忙しすぎて受け入れられない――ということが頻繁に起きるのです。
ゾンビテーマの評価を
せっかく提案しても、事業部が忙しすぎて受け入れられないとなると、コーポレート技術戦略部門も残念に思います。しかし、忙しいにも理由があります。それは「貧乏暇なし」という症状です。貧乏暇なしとは、要するに忙しいが儲かっていないということ。裏を返せば、儲かっていないテーマにリソースを投入している状態です。
そのため、リソース調整の問題が顔を出します。つまり、事業部では儲かっているテーマができているのか?できていれば儲かるはずではないか?儲かっているのなら技術の棚卸しはじめ横断的技術融合などする必要はないじゃないか?そういう疑問が出てくるわけです。
事業部では儲かるテーマを選択し、そこにリソースを配分できているのだろうか?仮にコーポレート技術戦略部門が技術の棚卸しに成功し、全社横断的な融合技術を事業部に提案できていたとすれば、その時点で自分たちの活動や提案内容にかなり自信を持っているはずです。それなのに事業部が受け入れないとするならば、相当な不満を持つはずです。つまり、技術の棚卸しを進めれば進めるほど、リソースの問題がつきまとうのです。
だからこそ、 技術の棚卸し以外にもう一つ必要なことがあります。それはゾンビテーマの見直しです。本当に今のテーマを続けるべきなのか。棚卸しを通じて、そんな問いが生じますので、それを潰していくことが、次の一歩を生み出していくのです。
研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます
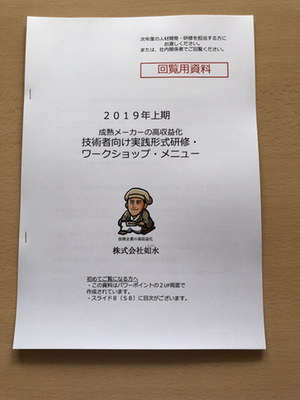
研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。
部署内でご回覧いただくことが可能です。
しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。
ご安心ください。
・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?
・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?
・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?
・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?
・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?
・新規事業化の体制構築を進めるには?
・最小で最大効果を得るための知財教育とは?