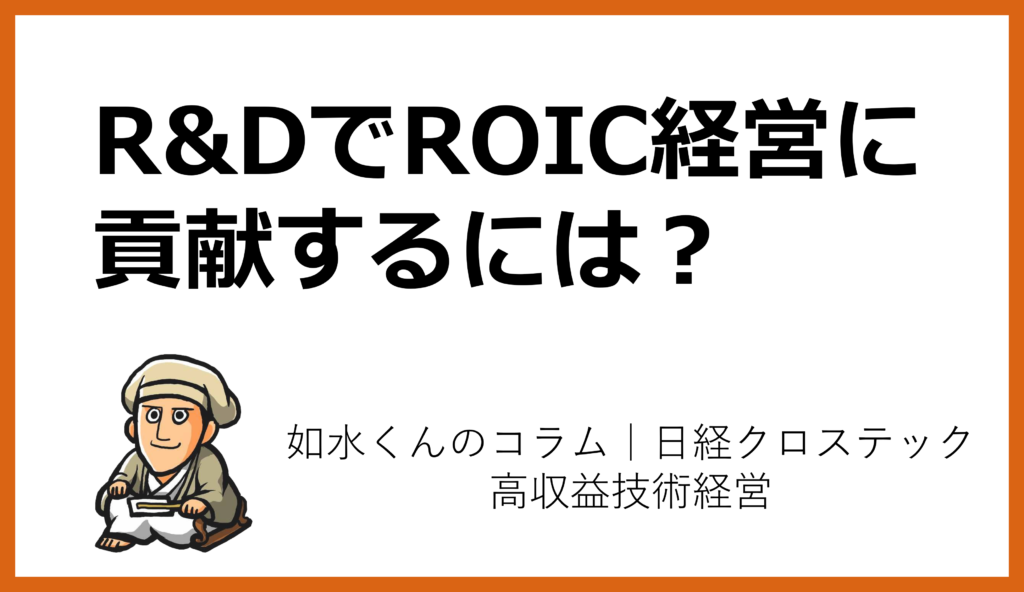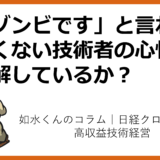「うちでもROICが言われるようになりました」技術者のため息混じりの声を、最近あちこちで耳にするようになった。背景にあるのは、東証によるプライム市場のPBR(株価純資産倍率)改善要請だ。 ROIC・PBRとR&D、見るからに面白くないテーマで、このコラムが読まれるかどうか心配だ。 とは言え、多くの方に役立つ内容だと信じるので勇気を持って書き進めてみよう。
釈迦に説法だが「PBR1倍割れ企業は、企業価値向上を」と問われ、企業価値をどう高めるかがあらためて議論されている。そこで、ROE(自己資本利益率)や、投下資本利益率=ROICが新たな物差しとして急浮上している。特にイヤなのは、事業部門に留まらず、R&D部門にまで「ROIC経営」の波が押し寄せていることではないだろうか?
R&Dの葛藤
一方で、R&D現場の多くはこう思っているはずだ。
「ROICなんて財務部門の話だろう?」
「R&Dは“将来のための投資”であって、目先の数字で語るものではない」
その感覚は、決して間違いではない。
現場にはこんな苦い記憶が残っているからだ。過去、ステージゲートやKPIを強化するたびに、「短期で数字化できないテーマ」が次々に排除されていった。目先の収益を説明できない研究や先行開発は、「採算が悪い」「投資対効果が薄い」として後回しにされ、そのたびに「やはりR&Dに数字管理は合わない」という実感が積み重なってきたのだ。
R&Dの数字化、過去の取り組みは
しかし、悔しいことにROICは“会社全体の数字”であると同時に、部門単位に具体化できる指標でもある。そして部門ごとに“見える化”しようという動きが、今、現実に進んでいる。「R&Dも数字で語れ」と言われるのは、もはや避けられない流れだ。避けたいものだが。
ただ、R&Dの効果はそもそも測りづらい。無理に数字で管理しようとすれば、現場が疲弊し、価値を生み出す余力が削られる。それでも、ROIC経営は確実にやってくる。この矛盾を、どう受け止めるべきなのか?
「研究と開発は異なる」
R&Dマネージャーなら、誰しも一度は思ったことがあるはずだ。「選択と集中の論理を、基礎研究にまで当てはめるのは違うだろう」と。事業部門における開発(D)で「選択と集中」が求められるのは納得できる。限られた経営資源を、勝てる市場・勝てる技術に振り向ける。これは競争の世界では当然の話だ。しかし、研究(R)にまで同じ尺度を適用するのは、明らかに違和感がある。
なぜなら、研究への投資は薄く広くの方が、長期的な成果につながるという実証研究が存在するからだ。日経新聞の報道でも、「研究開発はリスク分散によるポートフォリオ効果が重要」とされ、特定テーマへの過度な集中は、むしろ将来のイノベーション機会を損なうと指摘されている。
(参考:https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC19BFD0Z10C23A9000000/)
さらに、研究と開発が本質的に異なる理由は以下の表のように他にもある。
| 項目 | 研究 | 開発 |
| 目的 | 知の拡張・原理の発見 | 製品化・事業化 |
| 評価軸 | 新規性・論理性 | 収益性・市場適合性 |
| 成果の時間軸 | 長期・不確実 | 中短期・確度高め |
| 投資リスク | 分散型(ポートフォリオ効果) | 集中型(リターン重視) |
研究所で研究は行われているか?
願望だが、研究には「確実性」よりも「可能性」が重視されてほしい。一方で開発は、事業化・製品化と直結するため、経営資源の選択と集中が合理的に機能する。そこで部門ごとにマネジメントを変えれば良いと思われがちだが、「研究所」と呼ばれる組織が必ずしも研究だけをしているわけではないことがコトを難しくする。
実態として、多くの企業では「研究所」の中で開発行為が行われており、そこで求められるマネジメントは事業部に近い開発マネジメントをしている。逆に、事業部側でも先行開発に近い活動を研究と呼ぶケースもある。つまり、ラベルに惑わされず、「そのテーマは研究か開発か」「マネジメントすべきは知の探索か、事業化か」を見極める目線が、R&Dマネージャーには不可欠なのだ。
開発にとってのROICとは、「選択と集中」のルールである
既に触れた通り、「研究」と「開発」は異なる。そして、ROICという指標が本当にフィットするのは“開発”の方だと考えるのが自然だ。なぜなら開発は、製品や事業という出口に直結しており、経営資源(ヒト・モノ・カネ・時間)をどこに集中させるかが、直接企業価値に響くからだ。
このときROICは、単なる財務指標ではなく、「開発テーマを選ぶ/続ける/やめる」を決めるルールとして機能する。
ROICの基本公式を見ておこう。
ROIC=税引き後営業利益 ÷ 投下資本
シンプルに言えば、「使ったお金(資本)で、どれだけ稼いだか」を示す効率指標だ。ただ、現場にとってここでつまずくポイントがある。製品ごとの税引後営業利益(NOPATとも言う)や投下資本を、「現場レベルでは測っていない」「測れない」 という現実だ。
「ROICを意識しろ」と言われても、「どうやって?」「数字が取れないのに?」という違和感が噴き出すのは当然。そこで必要になるのは、ROICの思想を現場の“動かせる指標”に落とし込むことだ。言い換えれば、簡単に見える化できる“代替指標”が必要になるが、代替指標は管理会計に強く依存するため会社ごとに異なる。今日のコラムでは立ち入らずに開発でのROICの改善方法例に触れておきたい。
■ R&D(特に開発)がROICに貢献する3つの主要ポイント
1.営業利益への貢献(収益性向上)
製品の利益率をどう高めるかが、開発における最大の貢献ポイントだ。例えば、原価を下げる、売価を上げられる差別化機能を生む、その他、保守部品・サービスによる収益源を設計するなどがこれに当たる。しかし、顧客要望対応型の低収益開発の未だに続けていて、ゾンビテーマばかりになっている会社は少なくない。そのため、ゾンビテーマへの対処法がROIC経営のキーポイントになるだろう。
2.投下資本の抑制(資源配分・共通化)
次に、投下資本をどれだけ抑えられるか。例えば、開発テーマを進める際に、大型の専用設備を8時間稼働させるよりも、汎用設備や小型ユニットを24時間回すことで回転率を上げることができる。こうした設計思想の違いが、結果的に資本効率を大きく改善する。また、部品のモジュール化・共通化も同じ発想だ。しかし、多くの会社で個別最適が追記をされ、専用設備や専用部品等がいまだに多く存在するというのが現実だ。
3.投資回収スピード(フェーズゲート管理)
最後に、投資回収までのスピードだ。フェーズゲート管理は、この観点で非常に優れた発想だ。「見込みがあるかどうか」をフェーズごとにチェックし、ダメなら早めに止める。筋が良ければアクセルを踏むというのが理想だが、多くの企業でゾンビテーマを抱えている。見込める利益率が低くても、そのまま商品化してしまう会社が多いのではないだろうか? ここでもゾンビテーマ対処法がキーポイントになる。
以上が開発におけるROIC経営の基本的な考え方と適用例の一部だが、多くの会社でできていない実態がある事は想像に難くない。開発現場では適用余地が大きいことが想定できるのではないだろうか。
研究において、ROIC経営をどのように取り扱うべきか
では、研究においてはどうか。結論から言えば、研究にROICを“そのまま”適用しようとすると、歪みが生じるのは明らかだ。なぜなら、ROICは「資本をどれだけ効率的に回したか」を測る指標であり、そもそも成果の時間軸が長く、収益予測が困難な基礎研究とは、性質が異なるからだ。ではどうするのか?
1.研究は確率の世界なのでテーマのポートフォリオ管理に活かす
具体的には、短期で開発へ接続する“応用研究”、中長期の競争優位を見据えた“基盤技術研究”、10年単位の社会課題・破壊的イノベーションを見据えた“探索研究”になどに分類し、全体にまんべんなく投資する。つまり、「選択と集中」ではなく、リスクとリターンを分散するポートフォリオとして設計することで、企業全体のROICに貢献する。これが、研究におけるROICとの健全な付き合い方だ。
2.「ROICで測れないものは無駄」という短絡を避ける
絶対に注意したいのは「ROICで測れない=価値がない」という極論だ。これは危険な発想だ。そもそも基礎研究は、測れないからこそ取り組む価値がある領域だ。不確実性が高く、現時点で事業収益に結びつかなくても、未来の競争力や市場創出の種になるからこそ、長期的な投資対象として意味を持つ。ここに経営側が耐えられるだけの説明責任と、継続的なモニタリング(=ロジックベースでの可視化)が求められます。
3.技術者に将来構想を説明させる
個別の研究テーマに対して、ROIC(投下資本利益率)を一律に押し付けるべきではない。技術者に対してROICのような財務指標の計算を強いることなく、研究の本質に集中させることが重要だ。その代わりに、各テーマについて「なぜその研究を行うのか」という目的や意義を明確に言語化し、たとえ数値化が難しい価値であっても、戦略的意義や社会的意義、技術的優位性といった観点からロジックを構築させるべきだ。また、開発のように「選択と集中」を形式的に適用するのではなく、むしろ技術者個人に複数のテーマを立案させ、その中から継続・保留・中止といった判断を自律的に行える環境を整えることが、研究開発の質と主体性を高める上で効果的なマネジメントになる。
―と、ここまで書いているとちょっと長くなってしまった。ROICとR&Dという読者の関心がないと思われる禁断領域に踏み込んでいる気がするがまだまだ書くことがある。ここら辺で一区切りしておこうと思う。来月はROIC経営を適用するマネジメントをさらに深堀りしたいが、このコラムが読まれなければ別のテーマになるだろう。
研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます
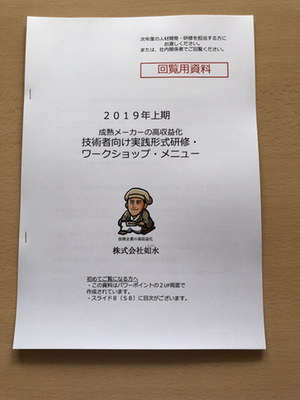
研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。
部署内でご回覧いただくことが可能です。
しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。
ご安心ください。
・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?
・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?
・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?
・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?
・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?
・新規事業化の体制構築を進めるには?
・最小で最大効果を得るための知財教育とは?