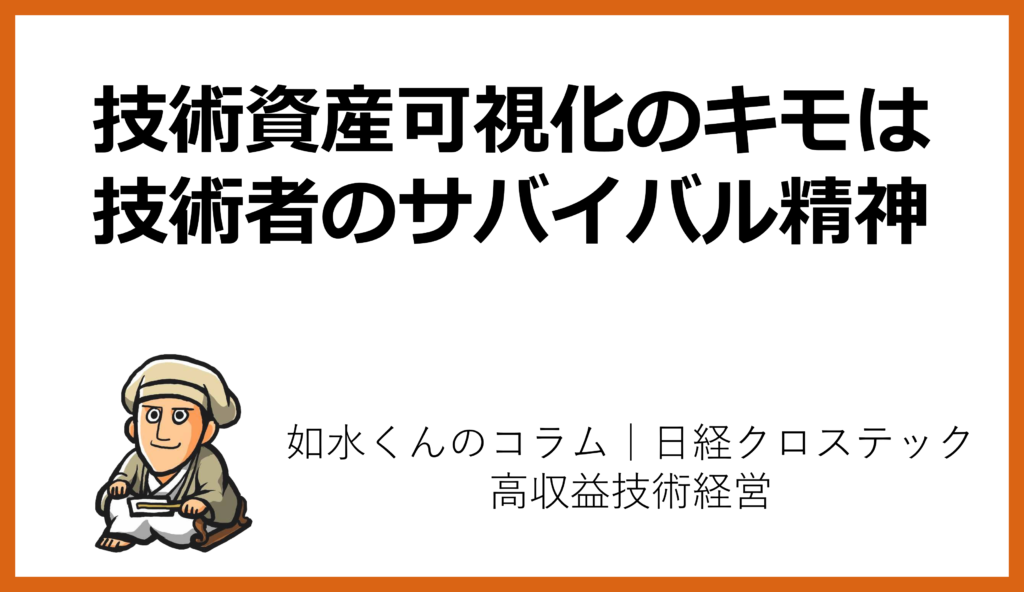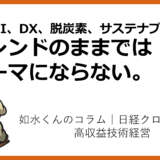「3Mのような形で、うちも技術の棚卸しをしてみたいんですよ」Aさんは真剣な眼差しでそう切り出しました。
棚卸しの目的は?
Aさんは、ある大企業の技術戦略部門のマネージャーです。落ち着いた口調で話す一方、どこか焦りのようなものが言葉の端々に滲んでいました。3Mの技術プラットフォームは著名事例として知られていますが、その事例を紹介する私のコラムを読んで私の会社に相談に見えられました。
動機についてお尋ねすると、「いま経営層からも『技術資産が有効活用されていない』とか、『技術部門が何をしているのか分からない』という声があがってきていて3Mって、社内技術の棚卸しを継続して、そこから新しい製品を生み出してきたというじゃないですか。うちも、ああいう“技術の見える化”をやりたいんです。それが、今の私のミッションなんです。」とAさん。
技術の棚卸し、ハマるワナ
私は、Aさんの顔から目を逸らしつつ、「なるほど。それがミッションなんですね」と言いました。「また同じワナにはまってるな」と思っていたので、お顔を見ることができなかったのです。
私はあえて次の質問を投げかけてみました。「仮定の質問ですが、3Mのように理想的な形で“見える化”ができたとします。そのとき、何が起こると思いますか?」Aさんは、少し考え込みました。そして、そのまま黙ってしまいました。
一覧表が揃って終わる、技術の棚卸し
私は続けました。「実は、多くの会社がその問いに答えられないまま、棚卸し作業だけを終えてしまうんです。つまり、技術資産の一覧表がきれいに整って、それで満足してしまう。でもそれでは、何も起きません。技術が動き出さないんです」
「ああ、確か別のコラムにも書かれていましたよね?」とよく私の過去記事を読んでいただいていたAさんは気づきました(その記事はこちら)。過去、技術資産の可視化をしたプロジェクトがその後どうなったのか、彼もご存知だったというわけです。
「儲かるテーマ創出が自分たちの仕事」という自覚がない
「でも、成功している会社には、決定的な違いがあるんです」と私は言葉をつなぎました。Aさんは聞く姿勢でした。「それは、技術者の“サバイバル精神”に火をつけていることです。」Aさんは眉を寄せ、首をかしげます。サバイバル精神というキーワードに疑問を持ったようでした。
私は続けました「サバイバル精神は『新しいテーマを自分で生み出さなければ、居場所がなくなるかもしれない』という感覚です。言い換えれば、『テーマ創出が自分の仕事』だという自覚を、技術者に本気で持たせている会社は、技術者のやる気にちゃんと火をつけている」
技術者のサバイバル精神とは?
Aさんはまだ納得できていないようでした。それでもゆっくりと頷きながら「なるほど……」と小さく呟きました。
Aさんはこれまで、技術資産の本格的な可視化を経験したことがありません。それゆえ、「技術の棚卸しによって何が起こるのか」という問いに対して、具体的なイメージを持てていなかったのも無理はありません。多くの企業と同じように、「可視化すれば何かが動き出すはずだ」という漠然とした期待が先行していたのでしょう。
私は、言葉を続けました。「技術資産の見える化って、見せ方の問題ではないんです。資料が綺麗にできたからといって、誰も行動を変えません。きれいに表にした、優位性を評価した、アクセス可能にした。それだけでは、技術者の心は1ミリも動かない。問題は、動機づけなんです」
Aさんは少し眉をひそめました。
「自分の仕事は自分で創る」意識
「たとえば、技術者自身が『次のテーマを自分で作らなければ、この部署に自分の居場所はないかもしれない』と本気で感じていたとしたらどうでしょうか?そのとき初めて、技術者は可視化された技術資産に手を伸ばすと思いませんか?」
Aさんは少し理解し始めたように静かにうなずいていました。技術者としてキャリアを積み、今はマネージャーとなった彼には、その心理がよくわかるのかも知れません。
「技術者にとって、テーマが与えられる環境は楽です。でも、自らテーマを創出することが求められるとき、彼らは初めて「テーマ創出に役立つ技術はないか?」と真剣に探し始めます。技術資産の見える化は、そういう自分の仕事を自分で作らなければ生き残れないという状況、つまりサバイバル精神を前提にしないと、ただの棚卸しで終わってしまう」私は、そう続けました。技術を「見せること」よりも、技術者自身が「見る必要に迫られること」が何より重要なのです。
私はさらに続けました。「結局のところ、技術資産の見える化が有効に働くかどうかは、それを“活用する必然性”が組織の中にあるかどうかで決まるんです。どれだけ綺麗な棚卸し資料を作っても、それを必要とする人がいなければ、ただの置物でしかありません」
Aさんは、少し考え込むような表情で黙っていました。
評価制度にも関係がある
「逆に、成功している会社では、現場の技術者に『次のテーマを自分で生み出さなければならない』という空気が浸透しています。その切実さがあるから、彼らは自ら技術資産に手を伸ばし、『この技術はどこで応用できるか』『今のテーマとどう組み合わせられるか』と、真剣に考えるようになる。見える化は、その時初めて意味を持ちます」
言い換えれば、可視化は技術者が動機づけられた時にのみ意味を持つのです。
「それって、制度や評価の仕組みとも関係があるんでしょうか」と、Aさんがぽつりと口を開きました。
「もちろんあります。それこそが本丸とも言えます。一般的に部下は上司に指示されなければ動きませんからね。上司に指示されなくてもテーマを創出するくらい元気な技術者もいるでしょうが、組織設計の前提にはなりません。」
私はそこで少し間を置き、こう締めくくりました。
「だからAさん、本当に大事なのは、見えるようにすることではなく、見ざるを得ない状況を作ることです。テーマ創出のプレッシャーをいい意味で与えれば、技術資産の見える化は一気に意味を持ちます。逆に、それがないまま始めても、やがて作っただけで終わるでしょう」
Aさんは深くうなずきながら、「なるほど……」と小さく呟きました。その表情には、今度こそ形だけで終わらせない、という決意が滲んでいました。
研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます
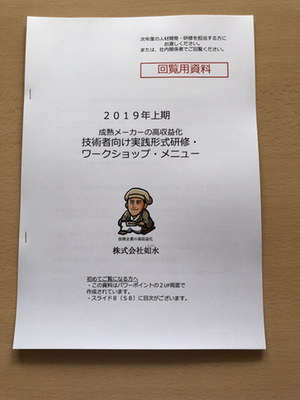
研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。
部署内でご回覧いただくことが可能です。
しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。
ご安心ください。
・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?
・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?
・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?
・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?
・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?
・新規事業化の体制構築を進めるには?
・最小で最大効果を得るための知財教育とは?