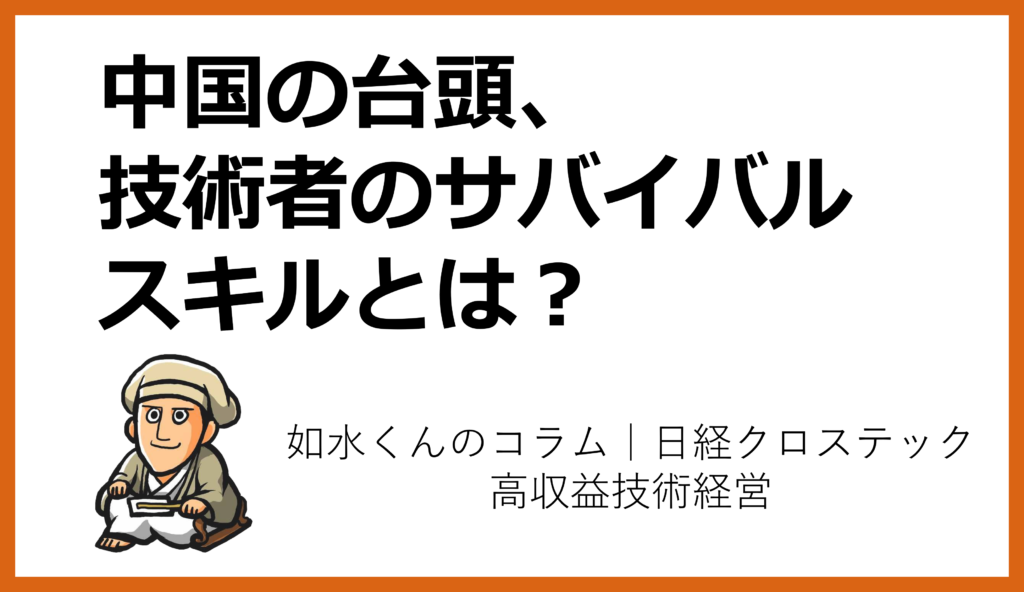北京で8月にロボット運動会が開催されました。従来、ロボコン(ロボットコンテスト)と言えば日本が私のイメージ。NHK主催のロボットコンテスト(高専生向け)や大学生・社会人などのロボコンが行われてきましたが、先月中国で行われたのは「運動会」でした。100m走をはじめとする競技。ヒューマノイドによる文字通りの「運動会」です。
ヒューマノイドは当然従来ロボットよりも複雑です。筆者が注目したのは、サッカー競技でした。サッカーではヒューマノイドが全て中国国内の企業から提供されたことです。競技者は世界各国から参加するものの、ソフトウェアを通じた競技になっていたのです。要するに、世界各国からの参加者はソフトウェアのみを開発して参加でき、ハードは中国企業が提供したとのこと。このことが我々に与える示唆が何かを今回のコラムでは考えてみたいと思います。
ロボット運動会
映像をご覧になった方はお分かりになると思いますが、ヒューマノイドは2足歩行し、また自分で立ち上がることのできるものでした。筆者が注目したのは、ヒューマノイドの数。サッカーができるほど、そして故障してもそれが変えられるほどの数を量産ができているということでした。
日本で行われるロボコンのロボットは一品物。予備機があってもせいぜい二台です。「運動会」といういわばコンテストでこの状況は、中国で量産が強く意図されていると言うことを示唆しているものと考えざるを得ませんでした。
従来ヒューマノイドと言えば、ペッパーやASIMOなどはせいぜい1体や数体でダンスなどの決められたタスクをこなすようなものでした。ティーチングは人間によってなされ、その通りにロボットが表現するといった程度のものでした。
一方、サッカーでは状況に応じてするべき事は変わりますし、それによってロボットに求められるタスクも変わります。判断するソフトは競技者が提供するとしても、それを身体的に表現できるハードウェアが必要になるわけです。これだけ複雑なハードウェアを量産できる力が中国国内に備わっているという事は、私たちは認めざるを得ないと思います。
ロボットだけでなく自動車も
ロボットだけではありません。自動車の力も特筆するべきものがあると思います。日本の高級車とほとんど遜色ない。あるいはそれ以上の高級車が中国の国産EV(またはPHEV)として、しかも私たち日本人がブランド名を知らないような中小規模なブランドも存在しています。中国は「世界の工場」を標榜していますが、その実力は製造のみでなく、研究や開発、設計の面にまでその力が及んでいると言う事を認めざるを得ません。
自動車に代表されるような巨大な市場で中国がこれだけ市場を伸ばしていること。またロボットのような今後巨大な市場になることが予想される市場でも同じような状況にある事は、その他の市場(例えば、半導体や工作機械など)のでも同じような景色が広がる(広がっている)ことを予想させるのではないでしょうか。
技術者のサバイバルスキルとは?
このコラムの読者には、中国企業にシェアを奪われている方も少なくないと思います。上記の情報は我々の仕事が従来通りでは生き残っていけないのでは?という不安を駆り立てるもののように思います。我々はどのようにしてサバイバルができるのでしょうか?以下ではこれを考えていきましょう。
まず、日本の特徴を概観しておくと、世界における日本の特徴は、産業の複雑が非常に高いことにあるされています。産業の複雑度とは、輸出品の多様性を示した指標です[1]。
日本はこの指標において非常に上位にづけられており、川上から川下までを輸出できる(国内で調達もできる)非常に恵まれた環境にあります。 このことが意味するのは、川下に当たる自動車やロボットなどの非常に複雑で部品点数が多岐にわたるような商品でも、国内生産し輸出することが可能という意味です。
自動車やロボットに見られる通り、もはや中国には生産量では及ばず、研究や開発の力でもかなり迫られていると言えます。ならば、小さな市場でトップシェアが取れるような開発をするっていうのが日本企業の大まかな戦略になると思います。いわゆる、ニッチトップ戦略です。
ニッチトップ戦略を実現するスキル形成を
なぜニッチトップなのか?それは自動車やロボットだけでなく、半導体や工作機械でも複雑な産業体系があれば高収益化しやすいからです。これが他国に比べて有利な環境ならば、その環境を活かしてニッチトップを具体化するのが個々の企業の戦略としてあってよいだろうと考えられます。
日本が産業の複雑度を維持し、個別企業がニッチトップ戦略を実現するには何が必要でしょうか?産業補助や税制優遇、教育支援など政策的な支援をすることは言うまでもなく必要ですが、このコラムでは、技術者にニッチトップ形成スキルが必要であることを強調したいと思います。様々な分野でニッチトップということは、その分野をつくる人が必要だということだからです。
ニッチトップを実現する他企業との連携
日々仕事をしていると見えにくいものの、産業の複雑度が世界一ということは、サプライヤーやお客様が国内にいっぱいいるということ。逆に言えば、他国企業(他国の技術者)はサプライヤーを国内には探しづらいということです。普段仕事をしている環境なので見えづらいものの、我々は恵まれた環境にあるのです。
そんな恵まれた環境を活かして、他社が模倣しづらい加工をするなどしてユニークなサプライチェーンを作り、高付加価値化して販売するということです。必ずしも起業する必要はありません。社内でテーマを立ち上げるだけで十分です。ただしその際に注意点があります。
従来通り社内技術で商品化しては従来通りになってしまいニッチトップが取れません。ニッチトップを取るには、他社の力を借りてニッチ市場への適合度合いを上げることが鍵になるでしょう(オープン・イノベーション)。
例を挙げると、手術ロボットというニッチ市場を狙って川崎重工とシスメックスが合弁会社(メディカロイド社)を立ち上げています。川崎重工にとってはロボット技術を手術用に特化させたものとなり、シスメックスにとっては医療分野の知見で新しいビジネスを狙うものとなります(ニッチを狙う戦略)。詳しくは、メディカロイド社のホームページをご覧ください。
話を戻すと、今後、日本の技術者のサバイバルに必要なスキルはニッチトップを作る力になるでしょう。やりやすい差異化は産業の複雑度を活かした高加工度、要するにニッチ市場に気の利いた機能にするということです。そうすれば他社(特に日本以外の他社)が追いつきづらくなるからです。換言すればオープン・イノベーションになります。
生物の世界では、環境に適した形に進化するのが生き残りのカギとされています。私達、技術者も環境に適応していくことが求められています。巨大市場の覇者(中国)が真横にいる環境で、日本という環境に適した戦略はニッチトップ。他社との連携で模倣困難なサプライチェーンを作るのはいかがですか?
[1] 経済複雑性指標(Economic Complexity Index 以下ECI)は、国の生産力の特徴を測る指標。ある国家のECIが「高い」ということは、その国家の輸出品目が多岐にわたっており、かつそれらが遍在性の低い(例えばヒューマノイドなどは開発できる国が限られており遍在性が低いといえる)品目であり、またそれらが多様性の高い国家で生産されていることを示す(参考、Wikipedia)。最新の調査では、日本は輸出部門で1位。詳細はこちら。
研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げます
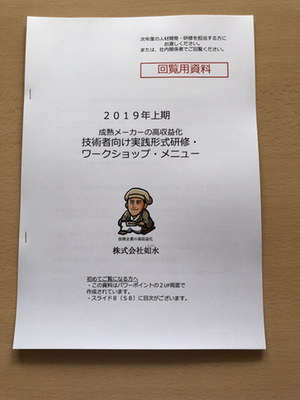
研究開発マネジメントの課題解決事例についてまとめた研究開発ガイドライン「虎の巻」を差し上げています。また、技術人材を開発するワークショップやコンサルティングの総合カタログをお送りしています。
部署内でご回覧いただくことが可能です。
しつこく電話をするなどの営業行為はしておりません。
ご安心ください。
・潜在ニーズを先取りする技術マーケティングとは?
・技術の棚卸しとソリューション技術カタログとは?
・成長を保証する技術戦略の策定のやり方とは?
・技術者による研究開発テーマの創出をどう進めるのか?
・テーマ創出・推進を加速するIPランドスケープの進め方とは?
・新規事業化の体制構築を進めるには?
・最小で最大効果を得るための知財教育とは?