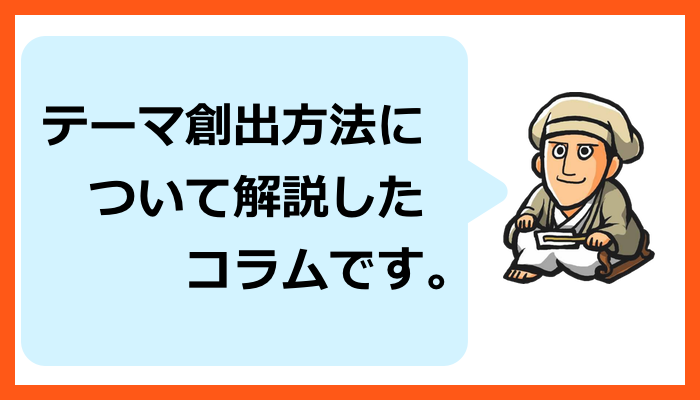株式会社如水
中村大介
目次
要約
2010年代の研究開発マネジメント
2020年代の研究開発マネジメント
アイデア考案方法
No input No IDEA
アイデアの要件1 独自性
アイデアの要件2 事業上の繋がり
アイデアの要件3 事業に必要な技術群
アイデアの要件4 知財
アイデア温め段階:研究開発マネージャーにとっての深掘りの仕組み
弱い会社は温めがうまくない
強い会社は温めがうまい
どのようにして運用強化するか
要約
本稿は研究開発テーマやアイデアを出す方法を解説するものである。筆者は研究開発と知財に関するコンサルタントであるため、守秘義務の関係上クライアントの秘密に当たるようなことは書けない。そこで、本稿では例え話でアイデアの量産体制の解説を試みることにする。
本稿を執筆しているのは2018年12月。足下では景気回復期間が戦後2番目の長さになったという。「オリンピックまでは」、「万博までは」景気がもって欲しいという希望があるが、早晩景気後退期が来るのは間違いない。そして景気は循環するものだ。その後再度景気回復期が来るだろうが、少子高齢化で移民政策でもとらない限り国内の成長が今以上に小さくなることは間違いないだろう。
本稿では、最初にこれまでの研究開発マネジメントを振り返り、2020年代が目前に迫る中、研究開発マネジメントにはどのようなことが求められるのかを展望することにしたい。
その上で、アイデア量産方法について検討する。
2010年代の研究開発マネジメントは「本業回帰」だった
思えば2018年末までの2010年代は、研究開発マネジメントの世界では本業回帰の時代ではなかったかと思われる。
2000年代は「失われた10年」、あるいは「20年」のまっただ中で、経営層からすぐに売れる商品を求められた。研究所と呼ばれる組織でも開発に近いことをしている組織が少なくなかった。
2000年代に入社した若手は現在では中堅である。極端な話だが、そんな元若手・現中堅にとっては、研究開発の仕事は「来年売れる商品を作ること」である。研究も開発もない。顧客ニーズを探して、競合と比較して負けないような商品開発をするのが研究開発の仕事であると思っている。そんな中堅に育てられる若手も益々そう思う。かつて、そんな循環があった。
2010年代になって企業業績が回復し、研究開発に求められるのは、短期的商品開発から中長期の成長戦略に変化した。研究と開発の分離が進んだ。研究機能の純化が図られたし、開発でも顧客ニーズと競合視点から脱した自社独自路線を目指そうとする動きがある。
そして、こうした純化に成功した会社は業績を伸ばしている。例えば、自動車業界ではマツダやスバルは独自路線が鮮明だ。一方、従来通り、顧客ニーズや競合比較の視点で短期的商品開発をしている会社では低粗利に苦しんでいるように見える。業界で「ミニトヨタ」と揶揄される某自動車メーカーなどはそれに当たるだろう。
研究が純化されて独自性を追求することになったという点と、開発でも競合比較ではなく独自路線が追求されやすくなったという意味で、まさに、2010年代は研究と開発の本業回帰の時代だったと言えるだろう。
2020年代の研究開発マネジメントに求められることは「技術獲得手段の多様化」である
目前に迫る2020年代は研究開発マネジメントにどのようなものを求めることになるのだろうか。
①本業回帰による成果の刈り取り
まず、2010年代の本業回帰時代に、中堅や若手の意識改革に成功した企業は研究開発の本業回帰で成果を出す時代になるだろう。すなわち、独自技術や独自製品が生み出される事が多くなるはずである。
残念ながら技術イノベーションはどの分野でもフロンティアがかつてほど広く・大きくはない。そのため、巨大市場を生むような斬新な製品は生まれにくいと思われるが、小さな市場で世界一というような商品が多数生まれるのではないかと思う。そうした成果を刈り取っていくことが必要であろう。
②独自技術獲得手法の多様化
2010年代、多くの会社が取り組んだオープンイノベーション、CVC(コーポレートベンチャーキャピタル)、スタートアップと共同は益々進んでいくことが予想される。NIH症候群(Not Invented Here 社内発明以外を排除しようとする組織風土)などは過去のものであり、技術を獲得するためであれば、社内でも社外でも関係はない、という組織文化が当然になるだろう。
現在では、外部技術の獲得手段としてのスタートアップの買収は一部先進企業に留まっているが、そうした手法もより一般化して多くの企業に利用されるようになるだろう。研究開発部門にはそうしたことへの対応も求められる。
③働き方改革
また、本来の意味での働き方改革も益々進むように思われる。2018年現在、働き方改革は単なる「時短」と捉える人も少なくないと思われる。しかし、筆者の考え方では、本来は働きたいように働いてより好きなだけ付加価値を創出するのが働き方改革ではないか。カジュアルに書けば「ノっている時」は残業しても休日出勤してもよく、「ノらない時」は会社に来なくても、付加価値さえ上げていれば問題ないことだ。
実際に、「20時以降の残業も認めて欲しい」という研究者の声を筆者が聞いたのは1度や2度ではない。単なる時短、残業禁止、休日出勤禁止という概念は早晩廃れるだろう。より本来的な意味での働き方改革が研究開発マネジメントにも求められる時代になるだろう。
④多様な採用
2018年の足下でも就職戦線は売り手市場であるが、大手よりも自らスタートアップを起こしたり、革新的な中小やベンチャーを志向する技術者が増加する傾向は続くだろう。現在のマネジメント世代から見れば、若手世代は十分優秀なように見えるだろうが、若手世代に欲がない事も同時に感じているのではないだろうか。
マネジメント世代が与えた仕事は優秀にこなすものの、自分で仕事を作り出すことはできず、テーマ探索などの何をしていいか分からないことには窮してしまう若手は少なくはない。
かつてのように、欲がある学生はもはや大手には来なくなっている。大手メーカーは自ら仕事を作り出せるような欲のある人材の確保には苦労することになる。そうした技術者は自ら仕事を作れる環境を求めている。
研究開発マネジメントに求められるのは、そうした人材が作り出した仕事をうまくインキュベーションする仕組み作りになる。小型の事業でのインキュベートできる仕組みがなければ、そうした人材は外に出て行く。インキュベーションする仕組みは、自社で製品化するだけでなく、多様な出口を確保することが必要になるだろう。
給料に対する意識は大きく変わるだろう。最近では人材不足のAI技術者は新卒で1500万円という事例もあるそうだ。会社から定額もらえる給料という概念は益々希薄になり、技術的知見や開発の成果としての報酬の意味合いが強くなるだろう。
以上のように、研究開発マネジメントに求められることが大きく変わっていくと思われるが、本稿のテーマであるアイデアやテーマの創造についてはどのようになるだろうか。次の項ではそのことを探ることにする。
アイデア考案方法
研究開発部門におけるアイデアやテーマの量産方法を、アイデア考案の段階と温めるという段階に分けて議論したい。まずはアイデア考案について、筆者の意見を紹介する。
残念ながら、個人レベルのアイデア考案方法について筆者は読者が知らないような革新的な方法を知っている訳ではないし、そうした方法はないと思う。
「失敗は成功のもと」、「必要は発明の母」、「天才とは1%の才能と99%の努力」など格言的なことが言われたが、昔と同様に今もそのまま当てはまると思う。
発明の方法としてはTRIZ、アイデアの具体化の方法としてはビジネスモデルキャンパス等の方法が知られているが、これらの方法は今も色あせていない。知っていれば誰でも素晴らしい成果が出せるという方法では当然ないが、普遍的で使える方法であると思う。
No input, No IDEA
ただし、上記のような方法を駆使しても革新的なアイデアが生まれるものではない。どんな天才発明家に言わせてもアイデアというのはインプットのないところには生まれないというのが筆者の意見だ。
例を二つ挙げよう。
一つ目。映画「博士と彼女のセオリー」で亡きホーキング博士がホーキング放射を思いつくシーンがある。映画ではホーキング博士が不自由な身体で着替えながら暖炉の炎を見るのだが、炎から何かが放射されているように見え、ブラックホールからなにかが放射されるという概念を思いつくのである。ここでは、炎を見たというインプットが描かれていた。
二つ目。真偽のほどは不明だが、エジソンは白熱電灯を発明する過程でフィラメントとして様々な材料を試した。あるとき、日本人が持っている扇子を見て、芯材になっている竹をフィラメントとして試したところ良好な結果を得て、白熱電灯の発明に一歩近づいたという逸話もある(諸説あります)。ここでは、当時エジソンにとって珍しかった日本人の持っていた扇子をインプットにしたため独自技術の獲得に成功したことを取り上げたい。
一方がなければ他方がないという意味で、No music, No lifeとか、No pain, No gainとか言うが、アイデアに関しては、No input, No IDEA だと筆者は強く信じている。
以上のように、アイデアはインプットなきところには生まれないというのが筆者の主張だが、どのように質の高い情報をインプットするか、に関しては研究開発の腕の見せ所だろう。
以下では、アイデアにはどのような要件が求められるかという観点からどのようにインプットするのかを概観したい。
アイデアの要件①独自性
企業である以上、アイデアは実行されることで競争優位を築けなければならない。そのため、他社が実施していないという意味の独自性が必要である。
インプットする情報に独自性がなければインプットの独自性がないというのは当然だ。他人と同じ情報に接していて、別のアイデアを思いつくのは不可能だ。
分かりやすく検討を進めるため、例を取り上げたい。本稿では、以下、「あんパン」という発明について取り上げて議論を進めることにしたい。
明治になって、文明開化の波が訪れると、西洋から来たパンというものとあんこを組み合わせたあんパンが生まれた。木村屋創業者木村安兵衛の発明と伝えられている。あんパンは、パンという、当時の日本では、ユニークな情報を仕入れたからこそ、思いついたアイデアと言えるだろう。
このように、インプットの独自性がなければ、アウトプットのアイデアも独自性がないのである。研究開発マネージャーとしては、インプットの独自性をいかにして担保するかが重要なことである。
「20XX年予測」というタイトルの書籍やレポートは市販されているため、技術者はこうしたものを元にしてアイデアを出すことがあるかも知れないが、こうした検討方法はアイデアを凡庸なものにしがちであり、注意しなければならない。
アイデアの要件②事業上のつながり
ただ、独自性があればいいというものでもない。例を挙げる。
引き続きあんパンの例で考える。仮に、和菓子屋さんがあんパンを思いつけば店先で売れるかも知れない。あんパンは和菓子の一種とも考えられるからだ。そして、あんパンの売れ行きが良ければ、別途パン屋さんを開くことも検討できるだろう。事業につながりがあるアイデアはとても良いものと言える。
一方、和菓子屋さんがフランスパンを思いついた場合を考えてみよう。フランスパンを和菓子屋さんの店先で売ることはしないだろう。畑違いに思えるからだ。そうすると、畑違いの商品の販売のためには別途店舗が必要になる。
経営視点から見れば、畑違いの事業のために店舗開設の巨額投資が必要になるように映るだろう。そうすると、実行が困難になる。事業的につながりが薄いアイデアは、その善し悪しは別として、事業につながりのあるものに比較して実行可能性が下がるのだ。
アイデアに独自性があれば良いというモノではないのだ。ケースバイケースではあるものの、一般的には事業上のつながりがある方が好まれる。
なお、事業上のつながりのないアイデアやテーマが必ず失敗すると言っている訳ではない。困難性を増すだけで、実現事例はもちろん、実現方法も一般化されていることは申し添えておく。
アイデアの要件③事業に必要な技術群
独自性があり、事業上のつながりがあれば良いのかと言えば、そうでもない。事業である以上、競争がある。競争に勝つためには、既存の商品を置き換えることができる程度の価格で生産できなければならない。
あんパンの例で考えてみよう。あんパンという市場がない中であんパンを売れば、競争相手がいないように見える。しかし、消費者はいくら独自性があって新しくても、あんパンが高額すぎれば消費を控えるというものだ。
和菓子屋さんの店頭に饅頭が100円で並んでいれば、どうしてもこれと比較してしまうだろう。あんパンを作るのがいくら難しく、原価がかかるものであっても、消費者には関係がない。あんパンをいくら食べたくても、あんパンが高ければ代わりのもので済ませてしまうだろう。
そうすると、あんパンは饅頭と同じ100円とまではいかなくても、近い金額にしなければ市場が大きくならないこと位は容易に想像が付くだろう。したがって、あんパンというアイデアに、あんパンを低価格で生産する技術が加わらなければ良いアイデアとは言えないことになる。
一般化すると、商品化のために必要な技術と事業のために必要な技術は異なる。上記の例で言えば、低価格生産技術となる。仮にあんパンを低価格で生産できるようになれば、その他のパンも低価格で生産できるようになる。あんパンという商品だけでなく、その他のパンを含む製パン事業が視野に入る。単なる商品化ではなく、広く市場に普及させようとすれば、必要となる技術の視座は広がらざるを得ないのだ。
アイデアの要件④知財
独自性、事業上のつながり、事業にするための技術群と見てきた訳だが、これだけでも事業にするには足りないように思う。
容易に模倣されてはいけない。そこで、知財が重要になる。
誤解のないようにしたいのだが、知財がとれればそれで良いという事は絶対にない。知財は模倣を防ぐための手段であり、模倣を防げない知財はとっても仕方がないものであると言える。
模倣を防げる知財とは、いわゆる基本特許と呼ばれるものであり、独自性のあるモノでなければ得られない。独自性がない(つまり、先行技術がある)分野では大した特許がとれないため、参入障壁としては機能しないからである。
あんパンの例で言えば、あんパンの基本特許はどのようなものか?
例えば、以下のように特許請求の範囲(クレーム)を記載したとする。
A案「あんをパン生地で包んだ食品」
一見、A案は良さそうに見えるが、模倣者の視点で見れば、「包む」というのが穴に見えるのではないだろうか。仮に、模倣者があんをパンでサンドイッチのようにした場合には、A案のクレームでは権利行使できない物になるだろう。コロネのような形状、コッペパンにあんこを挟むというものが出てきたとしても権利行使ができない。包んではいないからだ。
悪質な模倣者であれば、あんの一部を露出させることで、「包んではいない」という主張をする者も現れるかも知れない。
このように、あんパンを発明したと発明者が思っていたとしても、あんパンをそのまま権利にしたところで、実質的に事業を模倣されることになりかねないのだ。これらは、「包む」という点であんパンとは異なるが、消費者には実質的に同じだと捉えられ、実質的に事業を模倣される事となるかも知れない。そこで、別の基本特許のクレーム案が必要になる。
B案「あんとパンの接点のある食品」
B案のようにした場合には、サンドイッチでも権利行使しうるだろう。コロネのような形状であっても、コッペパンに挟むようなものでも権利行使できることとなる。そういう意味ではB案は良い権利ということとなる。
しかし、B案のようなものであっても、新規性・進歩性がなければ権利にならないことは言うまでもない。先行技術として同じものや近いものがあっては権利化できないのだ。
と、ここまで、良いアイデアの条件として、①独自性、②事業上のつながり、③事業に必要な技術群、④知財と見てきた。ここまで揃っていれば、良いアイデアであり、さらに実現可能性について調査してみたくなるのではないだろうか?
アイデア温め段階:研究開発マネージャーにとっての深掘りの仕組み
さて、次に、アイデアを温める段階について述べたい。
本稿はアイデアの量産体制をテーマとするものであり、研究開発マネージャーを主な読者層として想定している。
既に述べたとおり、最初は単なるアイデアでも、深掘りすることによって良いアイデアになるのだが、これはあくまでも技術者からみた視点の話である。研究開発マネージャーにとってより重要なのは、配下の多数の技術者が自ら手間暇をかけて深掘りする仕組みを作る事ではないだろうか?
アイデアは徐々に温められてよくなっていく
アイデアは徐々に温められて良いアイデアになるという性質を持っている。つまり、独自性、事業上のつながり、低価格生産技術、知財という要件をはじめから満たすようなアイデアはそもそも存在しない。どんなアイデアでも、最初は一つの要件しか満たしていないというのが通常である。徐々に温められる過程で、様々な検討がなされ、検討の過程で磨かれて行くのだ。
しかし、すべての会社でのこの温めの過程がうまくいくわけではない。コンサルタントとして様々な会社を見る立場にあるのだが、実に多くの会社で温めの過程が弱いのに気づく。そして、そうした会社の社員では、温めの過程が弱いということに気づいている人もいる。事業化の失敗が続いているとか、競合に負けてしまったとかいうことで失敗体験がついている場合もある。
どんなことに原因があるかと言えば、それは、制度というよりも運用、つまり人の問題であることがほとんどであると感じている。
温め過程が弱い会社でも強い会社と同様に、ステージゲート(温める仕組み)はある。このステージゲートを含めた会社の仕組みを「制度」という。制度については、弱い会社でも強い会社でも差はなく、ここに根本的な原因があることはない。
一方、制度の運用面では強い会社と弱い会社での差が顕著になると感じている。どういうことかあんパンを例に説明しよう。
弱い会社は温めがうまくない
まずは弱い会社。和菓子屋さんがあんパンという新規なものを考案したことは独自性があるものとして認められる。
あんパンの考案者は自信満々であり、あんパンの事業化に向けて技術開発の提案をしていく。
そしてサンプルワーク(サンプルワークとは、サンプルをユーザーに提供して試験的な評価をしてもらうこと)に移っていく。サンプルワークでは価格を提示せずに無料で提供するが、「美味しい」という評価が得られる。
ユーザー評価が高く、独自性があり、特許もとれそうということであるため、社内では競合がいないブルーオーシャンという認識をしている。そのため、販売価格としては、かかった原価に粗利を載せれば良いという程度にしか考えていない。
そして、満を持して発売と言うことになるのだが、饅頭が100円に対して販売価格は1000円と設定する。最初は物珍しさで売れていくが、しばらくするとサッパリ売れなくなる。
イノベーターやアーリーアダプターとマジョリティの間には谷があるからだ。ちなみに、この谷を専門用語では「キャズム」とも言う。弱い会社は技術的な事前準備が足りないため、キャズムを克服できないのだ。
上記はあくまで例え話とはいえ、弱い会社では、「独自性があるため、ブルーオーシャンで競合がいない」という説明が受け入れられる。単なる嗜好品としての商品としての捉え方しかしないため、市場を広げるための技術開発は意識されない。
別の書き方をすれば、提案者の周辺を取り巻く上司や評価者が甘いと言える。つまり、運用が甘いのだ。
強い会社は温めがうまい
一方、強い会社ではどうだろうか。
強い会社では、競合がいないのは良いことではあるが、消費者の視点での代替商品は何かを考える。そうして、饅頭が浮かび上がる。
饅頭は店頭で100円で売っている。そのため、消費者はあんパンがキャズムを克服して売れるようにするためには、饅頭と比較できる程度の金額で売れるようにしなければならないと考える。
強い会社ではイノベーターやアーリーアダプターとマジョリティのニーズが異なることを明確に認識している。そうして、低価格生産技術の開発に着手する。
強い会社でも最初は1000円で販売する。しかし、イノベーターやアーリーアダプターに販売した後、徐々に価格を下げていく。
そうして、最終的には饅頭よりも少し高いくらいに落ち着かせるだろう。饅頭はお菓子としての市場を確立している中、あんパンは日常食としての定着させることに成功し、市場が広がる。
また、低価格製パン技術を確立すれば、フランスパン等の別のパンの開発の基礎技術にもなることを、強い会社では認識している。次の事業展開をにらんでいるのだ。
このように、強い会社では事業にするための技術開発がなされるし、技術の連続性や転用についても意識された上で話が進む。運用が強固なのだ。
どのようにして運用強化するのか?
以上のように、強い会社と弱い会社は運用が違う。弱い会社は運用を強化しなければならないのだ。
運用を強化すると言えば、ステージゲートのゲート、つまり、審査を強くすることが思い浮かぶだろう。
しかし、審査を強化して良くなることはほとんどないと言って良い。
何故かと言えば、ゲートが強すぎて提案がことごとく却下されるからであり、ゲートキーパーは嫌われるし、提案者(技術者)のモチベーションは下がるからだ。組織風土は悪くなるしかない。
満点を要求すると提案者は確実なことしかしなくなることが心理学の世界では研究されているが、技術開発の世界では現実にそれが起こる。提案者は益々保守的なことしか言わなくなる。ゲートを強化しても良いことは何もないのだ。
では、運用を強化するには、誰がどうしたらいいのだろうか?
上記の通り、審査方式はいらない。アイデアの提案者には「促進者」が必要であるというのが筆者の主張だ。
促進者は、事業の発展や技術の連続性を理解して運用するのは当然として、会社として投資に見合うリターンが得られそうか、説明できなければならない。一般に技術開発のリターンは回収に時間がかかる。そのため目先の商品開発の投資対効果の説明と比較すれば、投資対効果の説明が難しいものとなる。こうした説明ができるように、アイデアを運用していく必要があるのだ。
あんパンの例で説明すると以下のようになる。
促進者はあんパンの提案者の同僚であると想定する。提案者の性格を想定すると、提案者は自ら考案したアイデアに得意げになっているかもしれない。提案者は独自性があるために、価格のことや市場を広げる事など全く考えずにとにかく開発したいと思っていることが多いと仮定する。
促進者はそうした提案者に対して、市場を広げるための考え方や、顧客の視点から見た競合の存在などに気づかせなければならない。提案者は意気揚々かもしれないが、それでは足りないことを、モチベーションを下げずに気づかせる必要がある。
ゲートキーパー等の第三者が評論家的な立場でこうしたこと指摘すると、提案者は「外野から関係ない人が好きなことを言っている」程度に受け取るのではないだろうか。指摘を無視する強さのある提案者ならまだ良いが、精神的に強くない提案者であれば指摘に窮してモチベーションを下げてしまうこともあるだろう。
モチベーションを下げさせないためには、信頼関係を獲得した同僚が促進者を担うのに適任である。ほとんどの場合、直属上司がそれに当たるだろうが、信頼関係を獲得していない状態では上司すらその任を担えない。
そのため、上司の能力向上こそが重要である。弱い会社ではここが欠如していることが多い。
上司強化の方法論
上司の能力向上とは、一般的な研修ではできない。育成が必要なのは「リーダーシップ」とか、「管理職研修」とかそんな中間管理職的なレベルではない。本気で事業化して中長期で採算をとっていくための真剣勝負のマネジメントを言っている訳である。甘い要素は一切ない経営者的視点のことを言っている。
私見ではあるが、このような真剣勝負ができる促進者は、その上司が真剣勝負する人でなければ育成されない。情けない上司のもとに、真剣勝負できる部下は生まれないと考えるのが健全である。真剣勝負できる部下は情けない上司を去るのが普通だからだ。
筆者はコンサルタントであるため、コンサルティングでこうした能力形成ができると書きたいところではあるが、実際のところ、コンサルタントがいくら頑張ったところで経営者を育成することなどできないと思っている。もちろん、促進者としての知識形成の研修はあって、実際に利用されている。しかし、真剣勝負のマネジメントの場は、研修の場では再現できない。
経営者には「修羅場」経験が必要だと一般的に言われるが、本当にそう思う。促進と言えば、聞こえは良いが、実際は促進だけではない。軌道修正のために、提案者のテーマをやめさせることも時にはしなければならないだろう。場合によっては、クビを切らなければならないかも知れない。まさに「修羅場」という言葉がふさわしい場面の覚悟がなければ良い促進者にはなり得ない。
研究開発マネージャーとしては、研修に加えて、こうした人材育成策を設定する必要がある。甘い場面ばかりの経験で、いい人材が育つことは絶対にないからだ。
終わりに
本稿では研究開発マネージャーのために、アイデア量産方法を解説した。アイデアの量産だけでなく、磨き上げるプロセスにも言及したつもりである。本稿を読んでくださっている皆様には、提案者と促進者をうまく共同させ、アイデア量産体制を作っていくことを期待したい。
本稿では本質的なことを書いたつもりではあるが、それがために、記載内容について私自身が最初に発見したことは何もないと思っている。それだけ先人達が残した技術経営的な資産は豊富であり、現在に生きる私たちはそうした知見に接するだけで視点が上げられるというのが現実だと思う。
最後に日本海海戦を勝利に導いた秋山真之が言ったという言葉を紹介して終わりたい。私はこうありたいと思っている内容だが、成果を上げたいと思う研究開発マネージャーにも同じ事が当てはまるだろうと思う。( )内は筆者による追記である。
「(作戦立案に際しては)必ず古今海陸の戦史をあさり、勝敗のよって来たるところを見極めさらには欧米諸大家の名論卓説を味読して要領をつかみ、もって自家独特の本領を要す。」
秋山真之